|
|
|
農家になるには? 農業で田舎暮らしを満喫するには? 無計画な田舎暮らしはじめて農業経営10年目、なりゆき農家の筆者が語る、日本の田舎と農村の、夢と現実。失敗しない新規就農、成功する田舎暮らしのコツ。兼業農家からアグリビジネスまで。 |
スポンサードリンク
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ここからつづき
◯自然条件「適地適作」を疑ってみよう
成功している(ように見える)産地をイメージしてみましょう。たとえば、ジャガイモといえば北海道、パイナップルといえば沖縄といった感じでしょうか。
しかし、必ずしもこれらが適地適作なのか疑問視してみることも必用です。たとえ産地だとしても、なりゆき上たまたまその作物になっていることも多いからです。もちろん理由がなりゆきでも、産地として成り立ってる以上、良い作物を生産しているのですから、そのこと自体をとやかく言ってはいません。ただ、ビジネスとして新規参入するあなたが、その歴史ある産地の活動に、途中から参加することがベストなのか?どうかです。
実際じゃがいもは、植物の生理的な面からみれば、どこでも作れますし、むしろ大敵であるウイルス病との関係を見るべきです。パイナップルも沖縄で露地栽培して本土まで運ぶ流通経費を考えれば、たとえば、大消費地の近くで温室栽培することも可能です。今後ますます温暖化が進むことも、冗談ではなく、本気で判断材料に入れなくてはいけません。
「適地適作」という考えは、昔のように季節の変化が毎年同じで、昔からの品種(固定種)を栽培するような場合に当てはまるものです。今の産地化された適地適作は、どちらかというとイメージ先行(というか、なりゆき)でできている場合もあります。現在の産地にこだわらずに、生産地と品目の関係を考えてみる必用があります。
またもし、有機栽培での新規就農を目指すのであれば、よりシビアに、かつ生物学的に慎重に場所を探すべきです。先駆者がいるからという理由で、その地域でやると簡単に決めてはいけません。日本で有機農法が、永続的にできるところは、ごく、限られています。
たとえば、トマトの有機農法を経営の核に考えた場合、都市近郊の平野部と、山奥の寒村と、どちらでやるか? 緯度はどこがいいのか? 標高はどれくらいのところがいいのか? あまり山奥で資材調達で失敗しないか? サビダニやコナジラミの発生状況はどうかなど、チェックすべき条件はいくらでもあるはずです。「適地適作」とは何なのか、より深く考えて、日本国内で有機農法が可能な自然環境とはどういうところなのか、温暖化や外来生物など、近い将来の変動要因も含めて、科学的に検討する必用があります。
マクロ的に生産地と品目の組み合わせの問題もありますが、具体的な農地の場所がより問題になることもあります。同じ村内でも、山裾の畑は風があたらないが、1km先の畑では季節風が強い、ということはあります。ミクロ的な環境で、その作物に適した畑はどういうものがベストかを考えておくことが必用です。場合によっては、産地だからできるだろうと思っていても、産地の中でも一定条件を満たす畑を手に入れない限り経済栽培ができない、ということも多々あります。
作物そのものにとっての生育環境以外にも、作物を育てる流れそのものが、どういうふうに組み立てられるのか?も、とても大事です。
たとえば、有機物の調達。野菜を中心にやろうと思っていても、近くに畜産農家や米農家があって、そこから堆肥や稲藁などの有機物が、永続的に供給してもらえるかどうか?などの要件もあるのです。土作りがしたくても、コスト的に満足のいく土づくりができない地域というのも、存在するのです。
その他にも、その地域の水(供給の仕方や水質)、里山の利用方(利用状況や権利関係)など、生産工程におおきく影響する自然条件があることを忘れてはいけません。
[参照]→科学的に適地適作を判定してみる…
◯自然条件「適地適作」を疑ってみよう
成功している(ように見える)産地をイメージしてみましょう。たとえば、ジャガイモといえば北海道、パイナップルといえば沖縄といった感じでしょうか。
しかし、必ずしもこれらが適地適作なのか疑問視してみることも必用です。たとえ産地だとしても、なりゆき上たまたまその作物になっていることも多いからです。もちろん理由がなりゆきでも、産地として成り立ってる以上、良い作物を生産しているのですから、そのこと自体をとやかく言ってはいません。ただ、ビジネスとして新規参入するあなたが、その歴史ある産地の活動に、途中から参加することがベストなのか?どうかです。
実際じゃがいもは、植物の生理的な面からみれば、どこでも作れますし、むしろ大敵であるウイルス病との関係を見るべきです。パイナップルも沖縄で露地栽培して本土まで運ぶ流通経費を考えれば、たとえば、大消費地の近くで温室栽培することも可能です。今後ますます温暖化が進むことも、冗談ではなく、本気で判断材料に入れなくてはいけません。
「適地適作」という考えは、昔のように季節の変化が毎年同じで、昔からの品種(固定種)を栽培するような場合に当てはまるものです。今の産地化された適地適作は、どちらかというとイメージ先行(というか、なりゆき)でできている場合もあります。現在の産地にこだわらずに、生産地と品目の関係を考えてみる必用があります。
またもし、有機栽培での新規就農を目指すのであれば、よりシビアに、かつ生物学的に慎重に場所を探すべきです。先駆者がいるからという理由で、その地域でやると簡単に決めてはいけません。日本で有機農法が、永続的にできるところは、ごく、限られています。
たとえば、トマトの有機農法を経営の核に考えた場合、都市近郊の平野部と、山奥の寒村と、どちらでやるか? 緯度はどこがいいのか? 標高はどれくらいのところがいいのか? あまり山奥で資材調達で失敗しないか? サビダニやコナジラミの発生状況はどうかなど、チェックすべき条件はいくらでもあるはずです。「適地適作」とは何なのか、より深く考えて、日本国内で有機農法が可能な自然環境とはどういうところなのか、温暖化や外来生物など、近い将来の変動要因も含めて、科学的に検討する必用があります。
マクロ的に生産地と品目の組み合わせの問題もありますが、具体的な農地の場所がより問題になることもあります。同じ村内でも、山裾の畑は風があたらないが、1km先の畑では季節風が強い、ということはあります。ミクロ的な環境で、その作物に適した畑はどういうものがベストかを考えておくことが必用です。場合によっては、産地だからできるだろうと思っていても、産地の中でも一定条件を満たす畑を手に入れない限り経済栽培ができない、ということも多々あります。
作物そのものにとっての生育環境以外にも、作物を育てる流れそのものが、どういうふうに組み立てられるのか?も、とても大事です。
たとえば、有機物の調達。野菜を中心にやろうと思っていても、近くに畜産農家や米農家があって、そこから堆肥や稲藁などの有機物が、永続的に供給してもらえるかどうか?などの要件もあるのです。土作りがしたくても、コスト的に満足のいく土づくりができない地域というのも、存在するのです。
その他にも、その地域の水(供給の仕方や水質)、里山の利用方(利用状況や権利関係)など、生産工程におおきく影響する自然条件があることを忘れてはいけません。
[参照]→科学的に適地適作を判定してみる…
PR
コ ン テ ン ツ
スポンサードリンク
面積の単位
1反(たん)
=300坪
=10アール(10a)
=10メートル×100メートル
=1000平米
1町(ちょう)
=10反
=1ヘクタール(1ha)
=100メートル×100メートル四方
私家版 農業田舎事典
農業現場で使われる用語/田舎暮しのキーワードなどの解説集。地域性などもあるので、あくまで筆者の独断と偏見に満ちた私家版です。ぼちぼち構築中です。
リンクサイト
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
サイト内検索
リンクサイト2
農業 GardenLinker
転職・転職活動
人気blogランキング

農業ブログリンク集!
田舎暮しの夢飛行船
◯田舎暮らしに役立つ情報サイトをご紹介する「田舎暮しの総合リンク集」です。
田舎暮らしと古民家物件
【田舎暮らし友の会】

田舎暮らしのネット

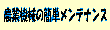
→農業機械のメンテナンス
転職・転職活動
人気blogランキング

農業ブログリンク集!
田舎暮しの夢飛行船
◯田舎暮らしに役立つ情報サイトをご紹介する「田舎暮しの総合リンク集」です。
田舎暮らしと古民家物件
【田舎暮らし友の会】
田舎暮らしのネット
→農業機械のメンテナンス
日豪EPAに関する検索結果
当サイト「田舎で農業を」を正しいレイアウトでご覧いただくには、windowsXP以上の環境が必要です。Windows2000でInternetExplorer6.0を使用した場合、正しく表示されませんので、Windows2000の方はFireFoxなどをご使用ください。
画像提供サイト
http://www.barrysclipart.com/
http://www.photolibrary.jp/
http://www.blwisdom.com/
http://www.printout.jp/clipart/
http://babu.com/~katus-gani/
http://www.kaocre.com/
http://www.barrysclipart.com/
http://www.photolibrary.jp/
http://www.blwisdom.com/
http://www.printout.jp/clipart/
http://babu.com/~katus-gani/
http://www.kaocre.com/

