|
|
|
農家になるには? 農業で田舎暮らしを満喫するには? 無計画な田舎暮らしはじめて農業経営10年目、なりゆき農家の筆者が語る、日本の田舎と農村の、夢と現実。失敗しない新規就農、成功する田舎暮らしのコツ。兼業農家からアグリビジネスまで。 |
スポンサードリンク
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
「農産物管理に必用な議技術は」からつづき
どんなに「近代的」「科学的」に人間がコントロールしてるつもりになっても、農業はけっきょく「自然まかせ」です。もちろん農業の生産現場は人為的な環境ですから、「調和のとれた大自然」という意味ではありません。人間の能力では処理できないぐらい莫大なファクターを含んだ相手という意味での自然です。「不可思議な自然」に働きかけて、そこから、生産物を得るのが農業の仕事です。
ですから、どんなに工夫をしたところで「根本的には安定生産なんてあり得ない」のが農業なのです。ただ、少しでも安定生産に近づこうということしか、できないのです。そのヘンを常に頭においておかないと、大きな失敗をすることになります。
U社の経営者は「衣料品のように計画生産ができなかった」と撤退時にコメントしたそうですが、まさか工業生産のように完璧に予定どおりの生産ができるとは思ってはいなかったでしょう。不確定要素が「想像以上だった」ということだと思います。このへんにも、農業の感覚と、ビジネスの感覚の、温度差みたいなものがみてとれるのではないでしょうか?
どの程度のラインまで農作物が安定供給できるか「読む」これは、実は、農業業界外の素人さんのみならず、農業現場の人間でも、なかなかできないことです。農協が出荷計画を立てるときも、農家の植付け面積と栽培状況をみて、データを積み上げていくのですが、なかなか収量予想は、当たりません。さらに、最近は温暖化による気象の変化もあって、プロの生産農家の生産予測の読みが当たりにくくなっていることもあります。
こうして、農産物販売は、常に、「供給数量の読み」にふりまわされているのです。
不安定な供給を、うまく経済システムにのせるためにできたのが、青果市場のセリ取引でしたが、相対取引や契約栽培が主流になり、セリが衰退してしまいました。確かに、以前に比べれば、「安定的な生産」になり、ある程度の契約取引が可能になりましたが、それでも工業製品のように予定どおりの生産は、絶対にありえません。
「契約栽培・契約取引」は農産物を買う側にとってはリスクが少なく販売計画が立てやすくなります。さらに「契約栽培」ということが、安心安全を証明するブランドになります。しかし、農家や流通業者にとては、必ずしも契約栽培なら絶対メリットがあるとはいえません。華やかな「契約栽培」という、ひとつのブランドの陰で、ロスの部分や、あるいは契約量を満たしきれない場合など、生産農家や流通業者が、陰で苦労して、損失をかぶっていることもあるのです。セリの平均値より、高めの値段で契約したとしても、けっきょく、不安定部分の補填をしなければならないので、手取り価格はセリとたいして変わらないということも、あると思います。
そもそも農産物の「契約」というのは、最終的には、農家を通して、植物と「契約」するわけです。自然相手ですから、人と人との契約のように履行されるとは限らないのです。
第2次3次産業の流通では、売るものが、人口的な生産物か人材(サービス)そのものです。そこでは、マーケティングと生産供給の連携をとることは充分可能です。たとえば、来月下旬に10日間キャンペーンを張るので、それに間に合わすように企画営業部から要請があったとします。生産部では、工場をフル稼働させたり、残業してがんばって、キャンペーン期間で提供する商品を確保するために全力を投入します。いろいろトラブルや問題があっても、社内で力を合わせて、時には社外の力も借りてがんばればなんとかなるのです。そんな感じでビジネスのドラマが日々繰り広げられているワケですが、ほとんどの仕事の現場では、不思議なことに、納期が間に合って何とかなるのです。ここが、人間の力、企業の力だと思います。がんばれば結果がでる。
しかし、一方、農産物の場合、相手が自然ですので、ダメな状況では、がんばってもどうしようもないことが多々あります。がんばったけど、「裏切られた」と思うことの連続です。最悪、今年はもう手遅れなので、来年がんばるしかない、となります。
手遅れにならないよう、先手先手をうって、できるだけ安定した栽培環境を整えるのが農家の仕事ですが、それでも何があるかわかりません。どうしようもない理由で、予定通りの生産ができないこと、がんばっても報われないことが、二次三次の産業にくらべて、あまりにも多いと思います。
そこを克服し、農業が他産業なみの収益を確保できるようにと、さまざまな技術や設備も提供されています。が、はたして、その技術や設備に投資して見合うだけの生産ができるのかどうか・・・そうした近代的新技術の導入を試算する時、「けっきょくは自然相手だからなぁ」という不確定要素に、また頭を悩まされるのです。
[参照]→契約栽培の課題と動向
(社団法人日本農村情報システム協会/アグリの杜より)
[参照]→信州がんこ村の契約栽培
(独立行政法人農畜産業振興機構/月報野菜情報より)
どんなに「近代的」「科学的」に人間がコントロールしてるつもりになっても、農業はけっきょく「自然まかせ」です。もちろん農業の生産現場は人為的な環境ですから、「調和のとれた大自然」という意味ではありません。人間の能力では処理できないぐらい莫大なファクターを含んだ相手という意味での自然です。「不可思議な自然」に働きかけて、そこから、生産物を得るのが農業の仕事です。
ですから、どんなに工夫をしたところで「根本的には安定生産なんてあり得ない」のが農業なのです。ただ、少しでも安定生産に近づこうということしか、できないのです。そのヘンを常に頭においておかないと、大きな失敗をすることになります。
U社の経営者は「衣料品のように計画生産ができなかった」と撤退時にコメントしたそうですが、まさか工業生産のように完璧に予定どおりの生産ができるとは思ってはいなかったでしょう。不確定要素が「想像以上だった」ということだと思います。このへんにも、農業の感覚と、ビジネスの感覚の、温度差みたいなものがみてとれるのではないでしょうか?
どの程度のラインまで農作物が安定供給できるか「読む」これは、実は、農業業界外の素人さんのみならず、農業現場の人間でも、なかなかできないことです。農協が出荷計画を立てるときも、農家の植付け面積と栽培状況をみて、データを積み上げていくのですが、なかなか収量予想は、当たりません。さらに、最近は温暖化による気象の変化もあって、プロの生産農家の生産予測の読みが当たりにくくなっていることもあります。
こうして、農産物販売は、常に、「供給数量の読み」にふりまわされているのです。
不安定な供給を、うまく経済システムにのせるためにできたのが、青果市場のセリ取引でしたが、相対取引や契約栽培が主流になり、セリが衰退してしまいました。確かに、以前に比べれば、「安定的な生産」になり、ある程度の契約取引が可能になりましたが、それでも工業製品のように予定どおりの生産は、絶対にありえません。
「契約栽培・契約取引」は農産物を買う側にとってはリスクが少なく販売計画が立てやすくなります。さらに「契約栽培」ということが、安心安全を証明するブランドになります。しかし、農家や流通業者にとては、必ずしも契約栽培なら絶対メリットがあるとはいえません。華やかな「契約栽培」という、ひとつのブランドの陰で、ロスの部分や、あるいは契約量を満たしきれない場合など、生産農家や流通業者が、陰で苦労して、損失をかぶっていることもあるのです。セリの平均値より、高めの値段で契約したとしても、けっきょく、不安定部分の補填をしなければならないので、手取り価格はセリとたいして変わらないということも、あると思います。
そもそも農産物の「契約」というのは、最終的には、農家を通して、植物と「契約」するわけです。自然相手ですから、人と人との契約のように履行されるとは限らないのです。
第2次3次産業の流通では、売るものが、人口的な生産物か人材(サービス)そのものです。そこでは、マーケティングと生産供給の連携をとることは充分可能です。たとえば、来月下旬に10日間キャンペーンを張るので、それに間に合わすように企画営業部から要請があったとします。生産部では、工場をフル稼働させたり、残業してがんばって、キャンペーン期間で提供する商品を確保するために全力を投入します。いろいろトラブルや問題があっても、社内で力を合わせて、時には社外の力も借りてがんばればなんとかなるのです。そんな感じでビジネスのドラマが日々繰り広げられているワケですが、ほとんどの仕事の現場では、不思議なことに、納期が間に合って何とかなるのです。ここが、人間の力、企業の力だと思います。がんばれば結果がでる。
しかし、一方、農産物の場合、相手が自然ですので、ダメな状況では、がんばってもどうしようもないことが多々あります。がんばったけど、「裏切られた」と思うことの連続です。最悪、今年はもう手遅れなので、来年がんばるしかない、となります。
手遅れにならないよう、先手先手をうって、できるだけ安定した栽培環境を整えるのが農家の仕事ですが、それでも何があるかわかりません。どうしようもない理由で、予定通りの生産ができないこと、がんばっても報われないことが、二次三次の産業にくらべて、あまりにも多いと思います。
そこを克服し、農業が他産業なみの収益を確保できるようにと、さまざまな技術や設備も提供されています。が、はたして、その技術や設備に投資して見合うだけの生産ができるのかどうか・・・そうした近代的新技術の導入を試算する時、「けっきょくは自然相手だからなぁ」という不確定要素に、また頭を悩まされるのです。
[参照]→契約栽培の課題と動向
(社団法人日本農村情報システム協会/アグリの杜より)
[参照]→信州がんこ村の契約栽培
(独立行政法人農畜産業振興機構/月報野菜情報より)
PR
コ ン テ ン ツ
スポンサードリンク
面積の単位
1反(たん)
=300坪
=10アール(10a)
=10メートル×100メートル
=1000平米
1町(ちょう)
=10反
=1ヘクタール(1ha)
=100メートル×100メートル四方
私家版 農業田舎事典
農業現場で使われる用語/田舎暮しのキーワードなどの解説集。地域性などもあるので、あくまで筆者の独断と偏見に満ちた私家版です。ぼちぼち構築中です。
リンクサイト
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
サイト内検索
リンクサイト2
農業 GardenLinker
転職・転職活動
人気blogランキング

農業ブログリンク集!
田舎暮しの夢飛行船
◯田舎暮らしに役立つ情報サイトをご紹介する「田舎暮しの総合リンク集」です。
田舎暮らしと古民家物件
【田舎暮らし友の会】

田舎暮らしのネット

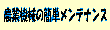
→農業機械のメンテナンス
転職・転職活動
人気blogランキング

農業ブログリンク集!
田舎暮しの夢飛行船
◯田舎暮らしに役立つ情報サイトをご紹介する「田舎暮しの総合リンク集」です。
田舎暮らしと古民家物件
【田舎暮らし友の会】
田舎暮らしのネット
→農業機械のメンテナンス
日豪EPAに関する検索結果
当サイト「田舎で農業を」を正しいレイアウトでご覧いただくには、windowsXP以上の環境が必要です。Windows2000でInternetExplorer6.0を使用した場合、正しく表示されませんので、Windows2000の方はFireFoxなどをご使用ください。
画像提供サイト
http://www.barrysclipart.com/
http://www.photolibrary.jp/
http://www.blwisdom.com/
http://www.printout.jp/clipart/
http://babu.com/~katus-gani/
http://www.kaocre.com/
http://www.barrysclipart.com/
http://www.photolibrary.jp/
http://www.blwisdom.com/
http://www.printout.jp/clipart/
http://babu.com/~katus-gani/
http://www.kaocre.com/

