|
|
|
農家になるには? 農業で田舎暮らしを満喫するには? 無計画な田舎暮らしはじめて農業経営10年目、なりゆき農家の筆者が語る、日本の田舎と農村の、夢と現実。失敗しない新規就農、成功する田舎暮らしのコツ。兼業農家からアグリビジネスまで。 |
スポンサードリンク
[新規就農概論] 農業法人にみるアグリビジネスの可能性
[2025/12/14] [PR]
[2007/03/29] 農業に参入するのはどんな企業?
[2007/04/10] 一般企業の撤退が・・・
[2007/04/11] 農産物管理に必用なのは、技術よりも感覚だ
[2007/03/29] 農業に参入するのはどんな企業?
[2007/04/10] 一般企業の撤退が・・・
[2007/04/11] 農産物管理に必用なのは、技術よりも感覚だ
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
「気づき系農業法人」からつづき
ここまで農業生産法人の分析をしてみましたが、ここから少しだけ、一般企業の農業参入をみてみましょう。
一般企業の農業参入を、経営陣が、どんな流れで農業をはじめてるかで、(多少,強引ですが)タイプ別に分類してみました。
◯帰農系 …もともと農家出身の社長。ほんとうは跡を継ぎたかったが、農業では喰えないので、自分は資格と技術を身につけ土建屋を起し、街で事業を展開してきた。今回の規制緩和を期に,故郷の村の遊休地で農業に本格参入。正直、土建が不景気なので、異業種参入という意味合いもある。
◯世直し系 …商売であたっている会社。はっきり言って,資金的には余裕がある。企業の本質は社会貢献だから、社長は、何か世の中のためになる新事業をしたい。やっぱり世の中の基本は農業だ! 最近の社長の関心事は、「健康長寿」でもあるので、「医食同源」をテーマにした、無農薬や有機栽培が多い。健康食品そのものの原料を作る場合もあり、健康食品が商品としてヒットすれば、農業的にも成功する。
◯技術系 …農業技術や制御管理などの技術メーカーが、自らの技術を証明すべく、実際の農業経営に乗り出している例。直営でやって上手くいかない場合、立場がなくなるので、ふつうの農業経営じゃ考えられないぐらいのお金と労力を使って、コンピューター管理の灌水空調システムで高糖度トマトを作るとか。野菜工場のモデルケースだが、どう考えても、農業部門だけで採算が合うとは思えない。
◯外食産業系 …材料まで独自ブランドにして店全体のブランド価値を高めるために、直営農場をもつのは、今や常識? 規格やら品種やらを、とにかく店舗側の要求応じて供給するためには、採算度外視の直営農場でないとなかなか対応できない。有機栽培農場がどこまで永続的に生産できるかが見物だが、農場の赤字くらい、いつでも補填できるので、会社のイメージ戦略が変わらない限り、なんとかなるんでしょう。
帰農系で母体が土建のところは、経営的には今後もビミョーかもしれませんが、社長はもともと農家だし、絶対いい人です。どちらかというと、「農」コースなのかもしれません。
世直し系と外食系は、とにかく、金はある。金があれば、なんでもできる。
そこをひがんでもしょうがないですから、しばらくは、「思いきり金をかければ、農業はできる」それとも「思いきり金をかても、農業はできない」のどっちなのか、結果を見守っていきたいと思います。
さて、これらの企業に就職するのは、もう、ふつうの就職と同じだと思います。はじめから農園枠でとるのか、配属で農場行きが決まるのかよくわかりません。
いずれにせよ、これらのところは、履歴書も写真貼付でしょうし面接も一応ネクタイしめていった方がいいんだと思います。やっぱり、新規就農って感じがしないなぁ・・・・。
[参照]→一般企業の農業参入事例
[参照]→農業正社員の例
ここまで農業生産法人の分析をしてみましたが、ここから少しだけ、一般企業の農業参入をみてみましょう。
一般企業の農業参入を、経営陣が、どんな流れで農業をはじめてるかで、(多少,強引ですが)タイプ別に分類してみました。
◯帰農系 …もともと農家出身の社長。ほんとうは跡を継ぎたかったが、農業では喰えないので、自分は資格と技術を身につけ土建屋を起し、街で事業を展開してきた。今回の規制緩和を期に,故郷の村の遊休地で農業に本格参入。正直、土建が不景気なので、異業種参入という意味合いもある。
◯世直し系 …商売であたっている会社。はっきり言って,資金的には余裕がある。企業の本質は社会貢献だから、社長は、何か世の中のためになる新事業をしたい。やっぱり世の中の基本は農業だ! 最近の社長の関心事は、「健康長寿」でもあるので、「医食同源」をテーマにした、無農薬や有機栽培が多い。健康食品そのものの原料を作る場合もあり、健康食品が商品としてヒットすれば、農業的にも成功する。
◯技術系 …農業技術や制御管理などの技術メーカーが、自らの技術を証明すべく、実際の農業経営に乗り出している例。直営でやって上手くいかない場合、立場がなくなるので、ふつうの農業経営じゃ考えられないぐらいのお金と労力を使って、コンピューター管理の灌水空調システムで高糖度トマトを作るとか。野菜工場のモデルケースだが、どう考えても、農業部門だけで採算が合うとは思えない。
◯外食産業系 …材料まで独自ブランドにして店全体のブランド価値を高めるために、直営農場をもつのは、今や常識? 規格やら品種やらを、とにかく店舗側の要求応じて供給するためには、採算度外視の直営農場でないとなかなか対応できない。有機栽培農場がどこまで永続的に生産できるかが見物だが、農場の赤字くらい、いつでも補填できるので、会社のイメージ戦略が変わらない限り、なんとかなるんでしょう。
帰農系で母体が土建のところは、経営的には今後もビミョーかもしれませんが、社長はもともと農家だし、絶対いい人です。どちらかというと、「農」コースなのかもしれません。
世直し系と外食系は、とにかく、金はある。金があれば、なんでもできる。
そこをひがんでもしょうがないですから、しばらくは、「思いきり金をかければ、農業はできる」それとも「思いきり金をかても、農業はできない」のどっちなのか、結果を見守っていきたいと思います。
さて、これらの企業に就職するのは、もう、ふつうの就職と同じだと思います。はじめから農園枠でとるのか、配属で農場行きが決まるのかよくわかりません。
いずれにせよ、これらのところは、履歴書も写真貼付でしょうし面接も一応ネクタイしめていった方がいいんだと思います。やっぱり、新規就農って感じがしないなぁ・・・・。
[参照]→一般企業の農業参入事例
[参照]→農業正社員の例
PR
「一般企業の農業参入って」からつづき
一般企業の問題点として、採算が合わなければすぐ撤退してしまうことがあげられます。
撤退といえば電子機器メーカーのO社や中国産衣料品ブランドのU社(脚注)の例が有名ですが、一般法人の農業参入が規制緩和された2005年9月以来、参入した184社のうち11社がすでに撤退しているということです(2007年3月日本経済新聞)。
これらの企業は、みな3年を待たずに撤退しています。
農業の3年というのは、ほとんどまだ何もやっていない状態に等しいです。幼稚園に3年通って今から小学生!という感じです。3年たってようやく何かが始まってきたという段階でしょう。
しかし一般のビジネスの感覚からすれば、たぶん3年でダメなら、何年やってもダメなのでしょう。優秀な経営者ほど、引き際も早いと思います。
おおむね農家は、(「ダメな」なりゆき農家にしろ「できる」農業生産法人にしろ)、10年〜20年あるいは1代2代という長いスパンで農業経営を考え、じっくりと大地に根を下ろして、農業に取り組んでいます。今はダメでも10年後にはなんとか見えてくるんじゃないか、そいうネバリをもって、みな農業経営に挑んでいます。多くの農作物は「1年に1作」です。1年1年の積み重ねで、ゆっくりした歩みで、技術や経営が改善されていくものです。
ですから、10年やって撤退ならまだ理解できますが、3年で撤退というのは、いろいろ事情があるにせよ、あまりにもお粗末といわざるをえません。
でもまぁここで企業の撤退を批判してもしょうがないので、このことから何を学ぶか?考えてみましょう。
ビジネス感覚の3年と農業時間の3年・・・この時間感覚の差、時の流れに対する感覚の温度差みたいなものが、ビジネスと農業が、実は、とっても「相性が悪い」ということを、象徴しているような気がします。
O社とU社の早期撤退。このふたつに象徴されるのは、農産物の「作る」難しさと「売る」難しさです。
筆者は業コースステップ1の章で、栽培技術革新と販売技術革新がアグリビジネスの必須条件だと述べました。今までのような作り方、今までのような売り方をしていたら、農業は生き残れない・・・・これはもうこの10年間いろんなところで言われていて、さんざん聞き飽きた言葉です。
非農家の新規就農や一般企業の農業参入を推進する論調の一部には、こんな理論があります・・・これまでの農家は、生産技術も販売営業も農協まかせで、安定生産の努力を怠り、マーケティングのマの字も考えなかったのだから、儲からないのは当たり前! 都会のビジネスで当たり前のことさえ導入すれば、農業は絶対に儲かるビジネスだ。
ホントに、安定生産と営業さえしっかりやれば農業が成り立つのか? そんなカンタンな話ではありません。そんなシンプルな話なら、O社もU社も撤退しないはずなのです。ただ普通に、生産ラインを改善し、マーケティングに力を入れれば業績が回復するか? そんなことはありません。
企業の撤退例は農業に対する読みが甘かったなんて言わずに、これだけ優秀な企業が見切っちゃうくらい、農業は難しいと解釈したほうがいいのじゃないでしょうか。
どんな栽培技術革新で、どんな販売技術革新をすればビジネスとしてなりたつのか? それとも、アグリビジネスは幻想なのか? 一般企業の早期撤退に何を学べばいいのか?
ビジネスとして農業を志向する人、農業法人への就職を考える人は、そのあたりを、よ〜く考えてみるべきだと思います。
脚注)U社の撤退…大人気格安衣料ブランドのU社の農業事業はあくまで流通に限られたものでしたので農業法人とはいえませんが、象徴的な例なので、あえて取り上げさせていただきます。
一般企業の問題点として、採算が合わなければすぐ撤退してしまうことがあげられます。
撤退といえば電子機器メーカーのO社や中国産衣料品ブランドのU社(脚注)の例が有名ですが、一般法人の農業参入が規制緩和された2005年9月以来、参入した184社のうち11社がすでに撤退しているということです(2007年3月日本経済新聞)。
これらの企業は、みな3年を待たずに撤退しています。
農業の3年というのは、ほとんどまだ何もやっていない状態に等しいです。幼稚園に3年通って今から小学生!という感じです。3年たってようやく何かが始まってきたという段階でしょう。
しかし一般のビジネスの感覚からすれば、たぶん3年でダメなら、何年やってもダメなのでしょう。優秀な経営者ほど、引き際も早いと思います。
おおむね農家は、(「ダメな」なりゆき農家にしろ「できる」農業生産法人にしろ)、10年〜20年あるいは1代2代という長いスパンで農業経営を考え、じっくりと大地に根を下ろして、農業に取り組んでいます。今はダメでも10年後にはなんとか見えてくるんじゃないか、そいうネバリをもって、みな農業経営に挑んでいます。多くの農作物は「1年に1作」です。1年1年の積み重ねで、ゆっくりした歩みで、技術や経営が改善されていくものです。
ですから、10年やって撤退ならまだ理解できますが、3年で撤退というのは、いろいろ事情があるにせよ、あまりにもお粗末といわざるをえません。
でもまぁここで企業の撤退を批判してもしょうがないので、このことから何を学ぶか?考えてみましょう。
ビジネス感覚の3年と農業時間の3年・・・この時間感覚の差、時の流れに対する感覚の温度差みたいなものが、ビジネスと農業が、実は、とっても「相性が悪い」ということを、象徴しているような気がします。
O社とU社の早期撤退。このふたつに象徴されるのは、農産物の「作る」難しさと「売る」難しさです。
筆者は業コースステップ1の章で、栽培技術革新と販売技術革新がアグリビジネスの必須条件だと述べました。今までのような作り方、今までのような売り方をしていたら、農業は生き残れない・・・・これはもうこの10年間いろんなところで言われていて、さんざん聞き飽きた言葉です。
非農家の新規就農や一般企業の農業参入を推進する論調の一部には、こんな理論があります・・・これまでの農家は、生産技術も販売営業も農協まかせで、安定生産の努力を怠り、マーケティングのマの字も考えなかったのだから、儲からないのは当たり前! 都会のビジネスで当たり前のことさえ導入すれば、農業は絶対に儲かるビジネスだ。
ホントに、安定生産と営業さえしっかりやれば農業が成り立つのか? そんなカンタンな話ではありません。そんなシンプルな話なら、O社もU社も撤退しないはずなのです。ただ普通に、生産ラインを改善し、マーケティングに力を入れれば業績が回復するか? そんなことはありません。
企業の撤退例は農業に対する読みが甘かったなんて言わずに、これだけ優秀な企業が見切っちゃうくらい、農業は難しいと解釈したほうがいいのじゃないでしょうか。
どんな栽培技術革新で、どんな販売技術革新をすればビジネスとしてなりたつのか? それとも、アグリビジネスは幻想なのか? 一般企業の早期撤退に何を学べばいいのか?
ビジネスとして農業を志向する人、農業法人への就職を考える人は、そのあたりを、よ〜く考えてみるべきだと思います。
脚注)U社の撤退…大人気格安衣料ブランドのU社の農業事業はあくまで流通に限られたものでしたので農業法人とはいえませんが、象徴的な例なので、あえて取り上げさせていただきます。
「一般企業の撤退に学ぶ」からつづき
O社の農業参入の例をみてみましょう。北海道千歳に7ヘクタールの広大なガラス温室を作って、室内の環境をできるだけ人為的にコントロールして工業製品なみに品質管理し、高糖度トマトを安定生産する計画でした。
O社は身近なところでは血圧計を作っていますが、センサーやリレーなどの電子制御部品の専門企業です。電子制御の技術を活かして、水やり・施肥や温度・湿度調整などの管理作業をコンピュータ制御して自動化することを目指していたようです。ちなみに高等度生産のノウハウは緑健農法と提携していました。技術部門はあと一歩のところまで技術を確立しかけていたが、経営陣が技術的確立を目の前に撤退を決めてしまったという内部事情もあるようです。
参入当時、農業業界でも相当話題になりましたが、ほとんどの農家は「コンピュータ制御でヤサイが作れるわけないよー」と思っていたので、「撤退」のニュースを聞いて、みんな正直ホットしたものです。
経営計画では、年産1400トンで売上7億円目標だったそうです。7町歩で1400トンということは反収20トン、1400トンで7億ということはキロ単価500円。まぁ不可能ではない目標数値ですが、この見込みをもとに18億円のハウス建設費を3年で償還するというのが甘すぎたようです。反収20トンという数値は、はいきなり初年度から出せるものではない、トマトでは最高クラスの収量です。どんな技術を使うにしろ、達成するには最低でも4〜5年はかかると考えるのが,常識です。
農業の栽培技術には「普遍性」は、あまりありません。その土地、その気候、その畑固有のものです。前にも書きましたが「技術は土地に付随している」とも言えるのです。
たとえば施設栽培であれば、ハウス一棟一棟、癖があります。土の性質だけでなく、風当たりや、湿気の持ち方など、微妙に違うのです。「土壌診断の数値では差が出なかったが、この棟は毎年木が出来過ぎになる窒素を控えめにしておこう」「このハウスは若干湿度が高いから、他のハウスより先に換気をはじめよう」このような細かい癖の部分まで、感覚的に捉えて管理することで、ようやく反収20トンのレベルに達するわけです。たとえば病害虫管理にしても、1年1年の失敗に学んでいかなければなりません。何年かやるうちに、その年の季節変化を肌で感じで「今年はヨトウムシが早く出そうだなぁ」など、病害虫防除技術が「勘」として身に付くようになるのです。
ようするに、農業技術とは、「感覚」や「勘」のしめる部分が大きいのです。「科学的な」農業技術ノウハウや農学は、自然現象のごく一部を切り取って見ただけにすぎません。実際の農業経営では、自分の育てる農畜産物の全体の状態を把握して、将来を予測して、できるだけ良い方向に持っていくことが必要です。野菜にしろ家畜にしろ、ひとつの生命活動体の健康状態を管理するのが農家の技術です。生命体の複雑で莫大な量の情報を処理するわけです。細かい科学的な数値やデータにふりまわされて、「木を見て森を見ず」になってはいけません。計算式やデーター集積は、参考にはなりますが、あくまでガイドラインを示すだけです。全体を感覚で大きく捉えなくてはいけません。そして、最後に決断を下すのは、「感覚」や「勘」です。
農業の技術を安定させていくには、五感六感をフルに活かして作物全体を捉え、自分の感性を信じて、年数をかけて結果を積み重ねていくしかありません。
使い古された言い方ですが、「自然相手だから」という一語につきます。コンピュータ制御をしても「自然相手ですから」うまくいくわけがないのです。
どうなるか予測不可能な自然から、すこしでもマシな安定生産ができるよう、せいぜいがんばってみること・・・農業の技術はそんなもんなのです。
さて、北海道千歳の7町歩のガラス温室は、その後どうなったかというと、後日談は以下の新聞記事をごらんください。
→北海道新聞「食業王国の道」
[参照]→ふつうのトマト農家の日々
O社の農業参入の例をみてみましょう。北海道千歳に7ヘクタールの広大なガラス温室を作って、室内の環境をできるだけ人為的にコントロールして工業製品なみに品質管理し、高糖度トマトを安定生産する計画でした。
O社は身近なところでは血圧計を作っていますが、センサーやリレーなどの電子制御部品の専門企業です。電子制御の技術を活かして、水やり・施肥や温度・湿度調整などの管理作業をコンピュータ制御して自動化することを目指していたようです。ちなみに高等度生産のノウハウは緑健農法と提携していました。技術部門はあと一歩のところまで技術を確立しかけていたが、経営陣が技術的確立を目の前に撤退を決めてしまったという内部事情もあるようです。
参入当時、農業業界でも相当話題になりましたが、ほとんどの農家は「コンピュータ制御でヤサイが作れるわけないよー」と思っていたので、「撤退」のニュースを聞いて、みんな正直ホットしたものです。
経営計画では、年産1400トンで売上7億円目標だったそうです。7町歩で1400トンということは反収20トン、1400トンで7億ということはキロ単価500円。まぁ不可能ではない目標数値ですが、この見込みをもとに18億円のハウス建設費を3年で償還するというのが甘すぎたようです。反収20トンという数値は、はいきなり初年度から出せるものではない、トマトでは最高クラスの収量です。どんな技術を使うにしろ、達成するには最低でも4〜5年はかかると考えるのが,常識です。
農業の栽培技術には「普遍性」は、あまりありません。その土地、その気候、その畑固有のものです。前にも書きましたが「技術は土地に付随している」とも言えるのです。
たとえば施設栽培であれば、ハウス一棟一棟、癖があります。土の性質だけでなく、風当たりや、湿気の持ち方など、微妙に違うのです。「土壌診断の数値では差が出なかったが、この棟は毎年木が出来過ぎになる窒素を控えめにしておこう」「このハウスは若干湿度が高いから、他のハウスより先に換気をはじめよう」このような細かい癖の部分まで、感覚的に捉えて管理することで、ようやく反収20トンのレベルに達するわけです。たとえば病害虫管理にしても、1年1年の失敗に学んでいかなければなりません。何年かやるうちに、その年の季節変化を肌で感じで「今年はヨトウムシが早く出そうだなぁ」など、病害虫防除技術が「勘」として身に付くようになるのです。
ようするに、農業技術とは、「感覚」や「勘」のしめる部分が大きいのです。「科学的な」農業技術ノウハウや農学は、自然現象のごく一部を切り取って見ただけにすぎません。実際の農業経営では、自分の育てる農畜産物の全体の状態を把握して、将来を予測して、できるだけ良い方向に持っていくことが必要です。野菜にしろ家畜にしろ、ひとつの生命活動体の健康状態を管理するのが農家の技術です。生命体の複雑で莫大な量の情報を処理するわけです。細かい科学的な数値やデータにふりまわされて、「木を見て森を見ず」になってはいけません。計算式やデーター集積は、参考にはなりますが、あくまでガイドラインを示すだけです。全体を感覚で大きく捉えなくてはいけません。そして、最後に決断を下すのは、「感覚」や「勘」です。
農業の技術を安定させていくには、五感六感をフルに活かして作物全体を捉え、自分の感性を信じて、年数をかけて結果を積み重ねていくしかありません。
使い古された言い方ですが、「自然相手だから」という一語につきます。コンピュータ制御をしても「自然相手ですから」うまくいくわけがないのです。
どうなるか予測不可能な自然から、すこしでもマシな安定生産ができるよう、せいぜいがんばってみること・・・農業の技術はそんなもんなのです。
さて、北海道千歳の7町歩のガラス温室は、その後どうなったかというと、後日談は以下の新聞記事をごらんください。
→北海道新聞「食業王国の道」
[参照]→ふつうのトマト農家の日々
コ ン テ ン ツ
スポンサードリンク
面積の単位
1反(たん)
=300坪
=10アール(10a)
=10メートル×100メートル
=1000平米
1町(ちょう)
=10反
=1ヘクタール(1ha)
=100メートル×100メートル四方
私家版 農業田舎事典
農業現場で使われる用語/田舎暮しのキーワードなどの解説集。地域性などもあるので、あくまで筆者の独断と偏見に満ちた私家版です。ぼちぼち構築中です。
リンクサイト
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
サイト内検索
リンクサイト2
農業 GardenLinker
転職・転職活動
人気blogランキング

農業ブログリンク集!
田舎暮しの夢飛行船
◯田舎暮らしに役立つ情報サイトをご紹介する「田舎暮しの総合リンク集」です。
田舎暮らしと古民家物件
【田舎暮らし友の会】

田舎暮らしのネット

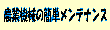
→農業機械のメンテナンス
転職・転職活動
人気blogランキング

農業ブログリンク集!
田舎暮しの夢飛行船
◯田舎暮らしに役立つ情報サイトをご紹介する「田舎暮しの総合リンク集」です。
田舎暮らしと古民家物件
【田舎暮らし友の会】
田舎暮らしのネット
→農業機械のメンテナンス
日豪EPAに関する検索結果
当サイト「田舎で農業を」を正しいレイアウトでご覧いただくには、windowsXP以上の環境が必要です。Windows2000でInternetExplorer6.0を使用した場合、正しく表示されませんので、Windows2000の方はFireFoxなどをご使用ください。
画像提供サイト
http://www.barrysclipart.com/
http://www.photolibrary.jp/
http://www.blwisdom.com/
http://www.printout.jp/clipart/
http://babu.com/~katus-gani/
http://www.kaocre.com/
http://www.barrysclipart.com/
http://www.photolibrary.jp/
http://www.blwisdom.com/
http://www.printout.jp/clipart/
http://babu.com/~katus-gani/
http://www.kaocre.com/

