|
|
|
農家になるには? 農業で田舎暮らしを満喫するには? 無計画な田舎暮らしはじめて農業経営10年目、なりゆき農家の筆者が語る、日本の田舎と農村の、夢と現実。失敗しない新規就農、成功する田舎暮らしのコツ。兼業農家からアグリビジネスまで。 |
スポンサードリンク
[新規就農概論] 進め!アグリビジネスマン
[2025/11/23] [PR]
[2007/03/12] 場所選びの3つの条件〜自然、経済、社会
[2007/03/13] 自然条件にみる、失敗しない就農地選び
[2007/03/14] 新規就農者の販売戦略とは
[2007/03/12] 場所選びの3つの条件〜自然、経済、社会
[2007/03/13] 自然条件にみる、失敗しない就農地選び
[2007/03/14] 新規就農者の販売戦略とは
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ここからつづき
失敗しない就農地選びのためのヒント
就農地選びは、就農の「準備」ではなく、もはや「あなたのビジネスそのもの」だ、ということは先に述べました。ですから、私が、これ以上、あなたのビジネスに口を挟むこともないのですが、一応、参考になればと思い、ヒントをいくつか挙げておきます。
農業をやる場所のことを考える場合、その場所のもつ、自然的条件、経済的条件、社会的条件の、三つの角度から考える必用があります。
もし、既存農家が、この3つの条件を活かして、経営のポリシーを描くとすると、たとえばこんなフレーズが出てきます。
◯自然条件を活かす…「適地適作」
◯経済的条件を活かす…「地産地消」
◯社会的条件を活かす…「地域に根ざす」
これらは、あくまでも地元農家にとってのスローガンで、地元役場と農協青年部のキャンペーンでやりそうな感じです。これらは、営農の歴史の延長線上にあってはじめて意味をもってくるものです。原点回帰みたいなものを、イメージアップと付加価値づけにして、なんとか発想の転換をしながら、夢を追いかけてみようという、よくわかるようでわからないような感じです。ここのところ混沌として先が見えない地元農家は、このスローガンでなんとか元気づけ、夢をつなぐのです。
「適地適作」「地産地消」「地域に根ざす」 このキーワードで地域のホームページを立ち上げ、ファーマーズマーケットを開き、道の駅でイベントを興し、そうこうしているうちに都会帰りのやる気のある後継者が加わって、地域がプチ成功するかもしれません。それを「農で起業」なんて言ったりもします。ですがこれは、あくまでプチ成功であって、それは、政治家や農水省やが期待するような、自立した(国際競争力のある!)農業経営とは、ほど遠いものだというのは、一目瞭然です。
プチ成功すればまだしも、ぐちゃぐちゃのまま空回りしてコケることも多いでしょう。このへんが、楽しくとも辛い、なりゆき農家集団の醍醐味といったところです。こんな楽しいなりゆき農家に付き合っていれば、基盤も資産もコネもない新規就農者は真っ先にチンボツします。あくまで、なりゆき系の世界ですので、アグリビジネスマンのあなたなら、一線をかくするべき世界でしょう。新規就農者がビジネスで成功するためには、よりクールで自由な新しい発想をしなければならないのです。
失敗しない就農地選びのためのヒント
就農地選びは、就農の「準備」ではなく、もはや「あなたのビジネスそのもの」だ、ということは先に述べました。ですから、私が、これ以上、あなたのビジネスに口を挟むこともないのですが、一応、参考になればと思い、ヒントをいくつか挙げておきます。
農業をやる場所のことを考える場合、その場所のもつ、自然的条件、経済的条件、社会的条件の、三つの角度から考える必用があります。
もし、既存農家が、この3つの条件を活かして、経営のポリシーを描くとすると、たとえばこんなフレーズが出てきます。
◯自然条件を活かす…「適地適作」
◯経済的条件を活かす…「地産地消」
◯社会的条件を活かす…「地域に根ざす」
これらは、あくまでも地元農家にとってのスローガンで、地元役場と農協青年部のキャンペーンでやりそうな感じです。これらは、営農の歴史の延長線上にあってはじめて意味をもってくるものです。原点回帰みたいなものを、イメージアップと付加価値づけにして、なんとか発想の転換をしながら、夢を追いかけてみようという、よくわかるようでわからないような感じです。ここのところ混沌として先が見えない地元農家は、このスローガンでなんとか元気づけ、夢をつなぐのです。
「適地適作」「地産地消」「地域に根ざす」 このキーワードで地域のホームページを立ち上げ、ファーマーズマーケットを開き、道の駅でイベントを興し、そうこうしているうちに都会帰りのやる気のある後継者が加わって、地域がプチ成功するかもしれません。それを「農で起業」なんて言ったりもします。ですがこれは、あくまでプチ成功であって、それは、政治家や農水省やが期待するような、自立した(国際競争力のある!)農業経営とは、ほど遠いものだというのは、一目瞭然です。
プチ成功すればまだしも、ぐちゃぐちゃのまま空回りしてコケることも多いでしょう。このへんが、楽しくとも辛い、なりゆき農家集団の醍醐味といったところです。こんな楽しいなりゆき農家に付き合っていれば、基盤も資産もコネもない新規就農者は真っ先にチンボツします。あくまで、なりゆき系の世界ですので、アグリビジネスマンのあなたなら、一線をかくするべき世界でしょう。新規就農者がビジネスで成功するためには、よりクールで自由な新しい発想をしなければならないのです。
PR
ここからつづき
◯自然条件「適地適作」を疑ってみよう
成功している(ように見える)産地をイメージしてみましょう。たとえば、ジャガイモといえば北海道、パイナップルといえば沖縄といった感じでしょうか。
しかし、必ずしもこれらが適地適作なのか疑問視してみることも必用です。たとえ産地だとしても、なりゆき上たまたまその作物になっていることも多いからです。もちろん理由がなりゆきでも、産地として成り立ってる以上、良い作物を生産しているのですから、そのこと自体をとやかく言ってはいません。ただ、ビジネスとして新規参入するあなたが、その歴史ある産地の活動に、途中から参加することがベストなのか?どうかです。
実際じゃがいもは、植物の生理的な面からみれば、どこでも作れますし、むしろ大敵であるウイルス病との関係を見るべきです。パイナップルも沖縄で露地栽培して本土まで運ぶ流通経費を考えれば、たとえば、大消費地の近くで温室栽培することも可能です。今後ますます温暖化が進むことも、冗談ではなく、本気で判断材料に入れなくてはいけません。
「適地適作」という考えは、昔のように季節の変化が毎年同じで、昔からの品種(固定種)を栽培するような場合に当てはまるものです。今の産地化された適地適作は、どちらかというとイメージ先行(というか、なりゆき)でできている場合もあります。現在の産地にこだわらずに、生産地と品目の関係を考えてみる必用があります。
またもし、有機栽培での新規就農を目指すのであれば、よりシビアに、かつ生物学的に慎重に場所を探すべきです。先駆者がいるからという理由で、その地域でやると簡単に決めてはいけません。日本で有機農法が、永続的にできるところは、ごく、限られています。
たとえば、トマトの有機農法を経営の核に考えた場合、都市近郊の平野部と、山奥の寒村と、どちらでやるか? 緯度はどこがいいのか? 標高はどれくらいのところがいいのか? あまり山奥で資材調達で失敗しないか? サビダニやコナジラミの発生状況はどうかなど、チェックすべき条件はいくらでもあるはずです。「適地適作」とは何なのか、より深く考えて、日本国内で有機農法が可能な自然環境とはどういうところなのか、温暖化や外来生物など、近い将来の変動要因も含めて、科学的に検討する必用があります。
マクロ的に生産地と品目の組み合わせの問題もありますが、具体的な農地の場所がより問題になることもあります。同じ村内でも、山裾の畑は風があたらないが、1km先の畑では季節風が強い、ということはあります。ミクロ的な環境で、その作物に適した畑はどういうものがベストかを考えておくことが必用です。場合によっては、産地だからできるだろうと思っていても、産地の中でも一定条件を満たす畑を手に入れない限り経済栽培ができない、ということも多々あります。
作物そのものにとっての生育環境以外にも、作物を育てる流れそのものが、どういうふうに組み立てられるのか?も、とても大事です。
たとえば、有機物の調達。野菜を中心にやろうと思っていても、近くに畜産農家や米農家があって、そこから堆肥や稲藁などの有機物が、永続的に供給してもらえるかどうか?などの要件もあるのです。土作りがしたくても、コスト的に満足のいく土づくりができない地域というのも、存在するのです。
その他にも、その地域の水(供給の仕方や水質)、里山の利用方(利用状況や権利関係)など、生産工程におおきく影響する自然条件があることを忘れてはいけません。
[参照]→科学的に適地適作を判定してみる…
◯自然条件「適地適作」を疑ってみよう
成功している(ように見える)産地をイメージしてみましょう。たとえば、ジャガイモといえば北海道、パイナップルといえば沖縄といった感じでしょうか。
しかし、必ずしもこれらが適地適作なのか疑問視してみることも必用です。たとえ産地だとしても、なりゆき上たまたまその作物になっていることも多いからです。もちろん理由がなりゆきでも、産地として成り立ってる以上、良い作物を生産しているのですから、そのこと自体をとやかく言ってはいません。ただ、ビジネスとして新規参入するあなたが、その歴史ある産地の活動に、途中から参加することがベストなのか?どうかです。
実際じゃがいもは、植物の生理的な面からみれば、どこでも作れますし、むしろ大敵であるウイルス病との関係を見るべきです。パイナップルも沖縄で露地栽培して本土まで運ぶ流通経費を考えれば、たとえば、大消費地の近くで温室栽培することも可能です。今後ますます温暖化が進むことも、冗談ではなく、本気で判断材料に入れなくてはいけません。
「適地適作」という考えは、昔のように季節の変化が毎年同じで、昔からの品種(固定種)を栽培するような場合に当てはまるものです。今の産地化された適地適作は、どちらかというとイメージ先行(というか、なりゆき)でできている場合もあります。現在の産地にこだわらずに、生産地と品目の関係を考えてみる必用があります。
またもし、有機栽培での新規就農を目指すのであれば、よりシビアに、かつ生物学的に慎重に場所を探すべきです。先駆者がいるからという理由で、その地域でやると簡単に決めてはいけません。日本で有機農法が、永続的にできるところは、ごく、限られています。
たとえば、トマトの有機農法を経営の核に考えた場合、都市近郊の平野部と、山奥の寒村と、どちらでやるか? 緯度はどこがいいのか? 標高はどれくらいのところがいいのか? あまり山奥で資材調達で失敗しないか? サビダニやコナジラミの発生状況はどうかなど、チェックすべき条件はいくらでもあるはずです。「適地適作」とは何なのか、より深く考えて、日本国内で有機農法が可能な自然環境とはどういうところなのか、温暖化や外来生物など、近い将来の変動要因も含めて、科学的に検討する必用があります。
マクロ的に生産地と品目の組み合わせの問題もありますが、具体的な農地の場所がより問題になることもあります。同じ村内でも、山裾の畑は風があたらないが、1km先の畑では季節風が強い、ということはあります。ミクロ的な環境で、その作物に適した畑はどういうものがベストかを考えておくことが必用です。場合によっては、産地だからできるだろうと思っていても、産地の中でも一定条件を満たす畑を手に入れない限り経済栽培ができない、ということも多々あります。
作物そのものにとっての生育環境以外にも、作物を育てる流れそのものが、どういうふうに組み立てられるのか?も、とても大事です。
たとえば、有機物の調達。野菜を中心にやろうと思っていても、近くに畜産農家や米農家があって、そこから堆肥や稲藁などの有機物が、永続的に供給してもらえるかどうか?などの要件もあるのです。土作りがしたくても、コスト的に満足のいく土づくりができない地域というのも、存在するのです。
その他にも、その地域の水(供給の仕方や水質)、里山の利用方(利用状況や権利関係)など、生産工程におおきく影響する自然条件があることを忘れてはいけません。
[参照]→科学的に適地適作を判定してみる…
ここからつづき
◯経済的要件「地産地消」のワナ
地産地消を当てにした販売戦略を、新規就農者はもつべきではありません。
地産地消という言葉はどうして生まれたのでしょうか? たとえば野菜で見てみましょう。10年近く前に大店法の規制緩和があって、田舎でも全国系列の大型スーパーが消費の中心としてすっかり定着しました。本来、地元の店だけの時は、野菜は地元近郊の農家が供給するパターンでした。スーパーは進出の時は、これまでどおり地元野菜を優先的に仕入れるという条件でしたが、地元野菜だけでは、やはり供給に不安定感があります。結局、名目的に少しだけ地元産を扱い、あとは系列の仕入れで、外国産も含む、全国の野菜を集めて売っています。
一方、多くの場合、地元の専業農家の野菜は、収益性の高い端境期(はざかいき)狙いで、遠くの大都市に出荷されます。これは、もともとスーパー進出の前からやっていたことで、地元で売るより高く売れるから、大都市に送るわけです。これをやれば、街のサラリーマン並みの収入が狙えるということでできたビジネスパタンです。ハウスや暖房が環境に悪いとか農協や経済連の中間搾取が多いとか、疑問も多いですが、けきょくまとまった金をとるには、これしかない。大消費地への出荷を優先して、厳しい農協(経済連)の規格でハネられたものが地元に供給される仕組みでした。
ところが、スーパーには外国産が並び、村のハウスの野菜は遠い都市部に出荷してる。こんな逆転現象は、どう考えてもオカシイんじゃないの? と、それに対するアンチテーゼとして「地産地消」の言葉が出てきたのです。
しかし、よく考えると、スーパーができる前は、大都市向け出荷ものの格外をはじめ、地元向けに作った野菜を地元野菜を地元で消費するのは、あたり前だったので、そんな言葉はなかったのです。
ある見方をすれば、この言葉、実は、スーパーが自からのイメージアップのために、ちょこっとだけ扱う地元野菜につけた、『地産地消』というブランド名なのです。スーパーがやっていることは、まず一回、地元野菜を追い出しておいて、地元野菜の希少価値を高めて、地元野菜をブランド化し、スーパーのイメージアップにつなげるわけです。イメージアップのためだから、青果コーナーのはじの棚から消えない程度に少しだけあればよいのです。
スーパーの表面的な地産地消戦略のおかげで溢れた地元野菜の売り先として、農協が用意したのが、「地産地消」と書かれたのぼりを立てたファーマーズマーケットです。地域にもよりますが、スーパーには毎日客が入りますが、ファーマーズマーケットでそこそこ売れるのは日曜だけ。でも地産地消だから、しょうがないか!って農家も思ったりして...あれれ?
つまり、「ビジネス」とは、このような、どこか道理に反したシカケによって、成立しています。大都市へ出荷する端境期のハウス野菜が「理に反してる」と言ってみても、スーパーのやり方を「姑息」だとか「汚い」と思っても、はじまりません。それがビジネスの世界です。
いずれにせよ、アグリビジネスを目指す新規就農者にとっては、地産地消でもないし、端境期の系統出荷でもないでしょう。もう少し別なベクトル、別な視点から販売モデルを構築していったほうがいいと思います。スーパーとか農協とかではなく、ある意味、次のバージョンの流通販売形態・・・成功するアグリビジネスの要件として、その具体的方法論をもって、新規就農しなければならないのです。
[参照]→地産地消の取り組み例
◯経済的要件「地産地消」のワナ
地産地消を当てにした販売戦略を、新規就農者はもつべきではありません。
地産地消という言葉はどうして生まれたのでしょうか? たとえば野菜で見てみましょう。10年近く前に大店法の規制緩和があって、田舎でも全国系列の大型スーパーが消費の中心としてすっかり定着しました。本来、地元の店だけの時は、野菜は地元近郊の農家が供給するパターンでした。スーパーは進出の時は、これまでどおり地元野菜を優先的に仕入れるという条件でしたが、地元野菜だけでは、やはり供給に不安定感があります。結局、名目的に少しだけ地元産を扱い、あとは系列の仕入れで、外国産も含む、全国の野菜を集めて売っています。
一方、多くの場合、地元の専業農家の野菜は、収益性の高い端境期(はざかいき)狙いで、遠くの大都市に出荷されます。これは、もともとスーパー進出の前からやっていたことで、地元で売るより高く売れるから、大都市に送るわけです。これをやれば、街のサラリーマン並みの収入が狙えるということでできたビジネスパタンです。ハウスや暖房が環境に悪いとか農協や経済連の中間搾取が多いとか、疑問も多いですが、けきょくまとまった金をとるには、これしかない。大消費地への出荷を優先して、厳しい農協(経済連)の規格でハネられたものが地元に供給される仕組みでした。
ところが、スーパーには外国産が並び、村のハウスの野菜は遠い都市部に出荷してる。こんな逆転現象は、どう考えてもオカシイんじゃないの? と、それに対するアンチテーゼとして「地産地消」の言葉が出てきたのです。
しかし、よく考えると、スーパーができる前は、大都市向け出荷ものの格外をはじめ、地元向けに作った野菜を地元野菜を地元で消費するのは、あたり前だったので、そんな言葉はなかったのです。
ある見方をすれば、この言葉、実は、スーパーが自からのイメージアップのために、ちょこっとだけ扱う地元野菜につけた、『地産地消』というブランド名なのです。スーパーがやっていることは、まず一回、地元野菜を追い出しておいて、地元野菜の希少価値を高めて、地元野菜をブランド化し、スーパーのイメージアップにつなげるわけです。イメージアップのためだから、青果コーナーのはじの棚から消えない程度に少しだけあればよいのです。
スーパーの表面的な地産地消戦略のおかげで溢れた地元野菜の売り先として、農協が用意したのが、「地産地消」と書かれたのぼりを立てたファーマーズマーケットです。地域にもよりますが、スーパーには毎日客が入りますが、ファーマーズマーケットでそこそこ売れるのは日曜だけ。でも地産地消だから、しょうがないか!って農家も思ったりして...あれれ?
つまり、「ビジネス」とは、このような、どこか道理に反したシカケによって、成立しています。大都市へ出荷する端境期のハウス野菜が「理に反してる」と言ってみても、スーパーのやり方を「姑息」だとか「汚い」と思っても、はじまりません。それがビジネスの世界です。
いずれにせよ、アグリビジネスを目指す新規就農者にとっては、地産地消でもないし、端境期の系統出荷でもないでしょう。もう少し別なベクトル、別な視点から販売モデルを構築していったほうがいいと思います。スーパーとか農協とかではなく、ある意味、次のバージョンの流通販売形態・・・成功するアグリビジネスの要件として、その具体的方法論をもって、新規就農しなければならないのです。
[参照]→地産地消の取り組み例
コ ン テ ン ツ
スポンサードリンク
面積の単位
1反(たん)
=300坪
=10アール(10a)
=10メートル×100メートル
=1000平米
1町(ちょう)
=10反
=1ヘクタール(1ha)
=100メートル×100メートル四方
私家版 農業田舎事典
農業現場で使われる用語/田舎暮しのキーワードなどの解説集。地域性などもあるので、あくまで筆者の独断と偏見に満ちた私家版です。ぼちぼち構築中です。
リンクサイト
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
サイト内検索
リンクサイト2
農業 GardenLinker
転職・転職活動
人気blogランキング

農業ブログリンク集!
田舎暮しの夢飛行船
◯田舎暮らしに役立つ情報サイトをご紹介する「田舎暮しの総合リンク集」です。
田舎暮らしと古民家物件
【田舎暮らし友の会】

田舎暮らしのネット

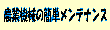
→農業機械のメンテナンス
転職・転職活動
人気blogランキング

農業ブログリンク集!
田舎暮しの夢飛行船
◯田舎暮らしに役立つ情報サイトをご紹介する「田舎暮しの総合リンク集」です。
田舎暮らしと古民家物件
【田舎暮らし友の会】
田舎暮らしのネット
→農業機械のメンテナンス
日豪EPAに関する検索結果
当サイト「田舎で農業を」を正しいレイアウトでご覧いただくには、windowsXP以上の環境が必要です。Windows2000でInternetExplorer6.0を使用した場合、正しく表示されませんので、Windows2000の方はFireFoxなどをご使用ください。
画像提供サイト
http://www.barrysclipart.com/
http://www.photolibrary.jp/
http://www.blwisdom.com/
http://www.printout.jp/clipart/
http://babu.com/~katus-gani/
http://www.kaocre.com/
http://www.barrysclipart.com/
http://www.photolibrary.jp/
http://www.blwisdom.com/
http://www.printout.jp/clipart/
http://babu.com/~katus-gani/
http://www.kaocre.com/

