|
|
|
農家になるには? 農業で田舎暮らしを満喫するには? 無計画な田舎暮らしはじめて農業経営10年目、なりゆき農家の筆者が語る、日本の田舎と農村の、夢と現実。失敗しない新規就農、成功する田舎暮らしのコツ。兼業農家からアグリビジネスまで。 |
スポンサードリンク
[新規就農概論] 進め!アグリビジネスマン
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ここからつづき
さてさて、話しが、なんか泥沼っぽい方向へ落ちていってしまいました。若干戻しまして、アグリビジネスマンのあなたが就農するステップをもう少し具体的に検討して、この章をまとめていきたいと思います。
アグリビジネスマンの就農ステップ
まず、情報収集をして営農モデルをどんどん試作する。このことは、いちばんはじめの「業コース、スッテプ2、3」で述べています。補足的に説明を加えますが、情報収集というのは、何もwebだけの情報ではありません。現場をいろいろ視察して、足で集める情報もあるでしょう。また、実際に自分で体験して得られる情報があります。そこで、今の仕事はやめずに、週末を使って、農業体験や研修をしてください。ただし、そこでは、技術を学んだとか経験を積んだと、勘違いしないでください。あくまで実体験に基づく情報を集めるだけなのです。あなたのビジネスに必用な技術や経験は、研修では身に付きません。研修は、あくまで体験にもとづく情報収集にすぎません。自分の営農をして、はじめて、自分に必用な技術と経験を実践できるのですから。
さて、情報集めの段階で、就農候補地の役所をいろいろあたって見ることをおすすめします。取り合ってくれないことも多いかもしれませんが、まずは顔を覚えてもらって、話しをきいてもらうことです。就農地候補というのは、あくまで、あなたの営農計画が実現可能である候補地のうちのひとつです。適当な農地が見つかったからと言って、そこに合わせるようにあなたの営農計画を変更するようなことはしないでください。あくまで、計画優先で、農地はいくつかある候補地から選ぶような流れにしてください。
さて、ある程度、経営が成り立つ営農モデルが完成したら、就農候補地で、あなたの事業を応援してくれる人を探さなくてはなりません。てっとり早いのは、役所の人です。
まずは、行政に話しをして、事業計画の実現性などを相談します。県の普及センターには新規就農相談の担当者がいますので、そこがいいでしょう。次に市町村農政係で事業の現実性を評価してもらってはどうでしょうか。次に農業委員会事務局から農業委員(=農家)を紹介してもらい、最後にいちおう農協にも顔を出すという感じで、関係機関にあなたの事業計画を話してまわります。
一昔前でしたら、この段階で門前払いですが、今はそんなことはありません。余所者のへの警戒は当然ありますが、あなたの計画の実現性があれば、しだいに認めてくれるはずです。情熱と誠意をもってあたれば、必ず糸口がつかめてきます。
あなたのビジネス計画を聞いているなりゆき農家なら、ここで引きますが、行政マンやできる農協職員は違います。ここで、客観的に、あなのビジネスの可能性を評価できないといけません。逆に、ビジネス的に話しができる行政マンがひとりもいないとなれば、その地域は候補地からはずしたほうが、後々のためにもよいでしょう。
ひつとつ注意することは、この段階はテンポよく進めなければなりません。公務員はすぐ移動するので担当が変わればゼロからやり直しだからです。
【関連記事】認定就農者
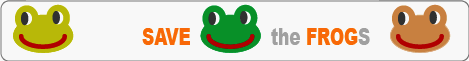
さてさて、話しが、なんか泥沼っぽい方向へ落ちていってしまいました。若干戻しまして、アグリビジネスマンのあなたが就農するステップをもう少し具体的に検討して、この章をまとめていきたいと思います。
アグリビジネスマンの就農ステップ
まず、情報収集をして営農モデルをどんどん試作する。このことは、いちばんはじめの「業コース、スッテプ2、3」で述べています。補足的に説明を加えますが、情報収集というのは、何もwebだけの情報ではありません。現場をいろいろ視察して、足で集める情報もあるでしょう。また、実際に自分で体験して得られる情報があります。そこで、今の仕事はやめずに、週末を使って、農業体験や研修をしてください。ただし、そこでは、技術を学んだとか経験を積んだと、勘違いしないでください。あくまで実体験に基づく情報を集めるだけなのです。あなたのビジネスに必用な技術や経験は、研修では身に付きません。研修は、あくまで体験にもとづく情報収集にすぎません。自分の営農をして、はじめて、自分に必用な技術と経験を実践できるのですから。
さて、情報集めの段階で、就農候補地の役所をいろいろあたって見ることをおすすめします。取り合ってくれないことも多いかもしれませんが、まずは顔を覚えてもらって、話しをきいてもらうことです。就農地候補というのは、あくまで、あなたの営農計画が実現可能である候補地のうちのひとつです。適当な農地が見つかったからと言って、そこに合わせるようにあなたの営農計画を変更するようなことはしないでください。あくまで、計画優先で、農地はいくつかある候補地から選ぶような流れにしてください。
さて、ある程度、経営が成り立つ営農モデルが完成したら、就農候補地で、あなたの事業を応援してくれる人を探さなくてはなりません。てっとり早いのは、役所の人です。
まずは、行政に話しをして、事業計画の実現性などを相談します。県の普及センターには新規就農相談の担当者がいますので、そこがいいでしょう。次に市町村農政係で事業の現実性を評価してもらってはどうでしょうか。次に農業委員会事務局から農業委員(=農家)を紹介してもらい、最後にいちおう農協にも顔を出すという感じで、関係機関にあなたの事業計画を話してまわります。
一昔前でしたら、この段階で門前払いですが、今はそんなことはありません。余所者のへの警戒は当然ありますが、あなたの計画の実現性があれば、しだいに認めてくれるはずです。情熱と誠意をもってあたれば、必ず糸口がつかめてきます。
あなたのビジネス計画を聞いているなりゆき農家なら、ここで引きますが、行政マンやできる農協職員は違います。ここで、客観的に、あなのビジネスの可能性を評価できないといけません。逆に、ビジネス的に話しができる行政マンがひとりもいないとなれば、その地域は候補地からはずしたほうが、後々のためにもよいでしょう。
ひつとつ注意することは、この段階はテンポよく進めなければなりません。公務員はすぐ移動するので担当が変わればゼロからやり直しだからです。
【関連記事】認定就農者
PR
ここからつづき
あなたの営農計画が、地域の役所や農業委員にある程度認められれば、いよいよ、実際の就農地をどう確保するか? という話しなります。
新規就農者のための農地が、あるかないか? たとえあったとしても出てくるか?出てこないか?は、市町村単位で、それぞれの事情によっていろいろです。すぐ農地銀行の農地が出てくる場合もあるし、実際問題、農地が空いてないこともあります。ですから、あなたの営農モデルを実践可能な就農地の候補地は、いくつかないといけません。ぶっちゃけ、市町村への就農相談は、二股三股かけるかたちで、進めてください。
郷土愛の強い地域なら二股かけられると心象をすこし悪くしますが、そんな些細なこと(地域的には大問題ですが、ビジネス的には些細なことです)はブッチギってください。郷土愛のような「なりゆき的要素」を、クールに排除してください。就農地選びの段階で失敗しないためです。
さて、ここで、問題になるのは、農地を新参者のあなたに斡旋する場合に、やはりどうしても「実績」が問われることです。たいていは、実績作りのために、地域の先進農家で最低1年くらいは研修してください、と言われます。
この実績作りなんですが、これが、新規就農者にとっては、ミソです。1年研修をやって、すぐ自作農地が見つかればよいのですが、気付くと研修も3年目・・・なんてことも多々あります。そうなると、もはや研修ではなく、「実績作り」という名のもとに捨てておかれているだけです。
これまで、この「実績作り」というハードルのために、多くのビジネス的新規就農者が、なりゆき農家に転落してきました。すばらしいアイデアとバイタリティーを持って田舎にやってきたとしても、農地を確保するために「実績作り」を要求され、数年間研修や農業バイトをして暮らし、バイタリティーとアイデアが萎んでしまい、気がつくとなりゆき農家になっている、あるいは、やっぱり就農はやめている、そんなケースがよく見られます。
農業生産法人などで研修することは、あるい意味、研修といっても、ようはコネ作りです。研修受け入れ側としても研修生を使うのは、補助金がついて安い労働力として使えるから、てなケースもあります。もちろん、研修先の先輩は、後輩を育てようという気持ちがあってやってることですから、そういう包容力のある経営主からは、人として学ぶことは大きいでしょう。ただし、そこで用いられている栽培技術やビジネスの方法論が、あなたの就農計画で使えるものとは限りません。むしろ、あなたの計画とかけ離れていることの方が、多いかもしれません。
研修先では、先輩農家の技術や経営方針を、そっくり学ぶわけではありません。ある部分は真似して、ある部分は反面教師にする。そのへんの情報収集もありますが、原則、農業は、畑が違えば方法論も全て違ってきますので、最終的には、技術は自分自身で会得するしかありません。研修は、技術習得ではなくあくまで参考になるだけです。他人の畑で3年勉強したって、自分の畑ではゼロからまたやり直しです。農業の技術は、人に習うものではないのです。言い換えれば、農業技術はその土地に付随した固有のものだとも言えるのです。
ですから、新規就農者の就農計画がしっかりしてるものであればあるほど、研修とは、コネ作り以外に、あまり意味をもたいない、ということが言えるのです。
【関連記事】就農支援資金
あなたの営農計画が、地域の役所や農業委員にある程度認められれば、いよいよ、実際の就農地をどう確保するか? という話しなります。
新規就農者のための農地が、あるかないか? たとえあったとしても出てくるか?出てこないか?は、市町村単位で、それぞれの事情によっていろいろです。すぐ農地銀行の農地が出てくる場合もあるし、実際問題、農地が空いてないこともあります。ですから、あなたの営農モデルを実践可能な就農地の候補地は、いくつかないといけません。ぶっちゃけ、市町村への就農相談は、二股三股かけるかたちで、進めてください。
郷土愛の強い地域なら二股かけられると心象をすこし悪くしますが、そんな些細なこと(地域的には大問題ですが、ビジネス的には些細なことです)はブッチギってください。郷土愛のような「なりゆき的要素」を、クールに排除してください。就農地選びの段階で失敗しないためです。
さて、ここで、問題になるのは、農地を新参者のあなたに斡旋する場合に、やはりどうしても「実績」が問われることです。たいていは、実績作りのために、地域の先進農家で最低1年くらいは研修してください、と言われます。
この実績作りなんですが、これが、新規就農者にとっては、ミソです。1年研修をやって、すぐ自作農地が見つかればよいのですが、気付くと研修も3年目・・・なんてことも多々あります。そうなると、もはや研修ではなく、「実績作り」という名のもとに捨てておかれているだけです。
これまで、この「実績作り」というハードルのために、多くのビジネス的新規就農者が、なりゆき農家に転落してきました。すばらしいアイデアとバイタリティーを持って田舎にやってきたとしても、農地を確保するために「実績作り」を要求され、数年間研修や農業バイトをして暮らし、バイタリティーとアイデアが萎んでしまい、気がつくとなりゆき農家になっている、あるいは、やっぱり就農はやめている、そんなケースがよく見られます。
農業生産法人などで研修することは、あるい意味、研修といっても、ようはコネ作りです。研修受け入れ側としても研修生を使うのは、補助金がついて安い労働力として使えるから、てなケースもあります。もちろん、研修先の先輩は、後輩を育てようという気持ちがあってやってることですから、そういう包容力のある経営主からは、人として学ぶことは大きいでしょう。ただし、そこで用いられている栽培技術やビジネスの方法論が、あなたの就農計画で使えるものとは限りません。むしろ、あなたの計画とかけ離れていることの方が、多いかもしれません。
研修先では、先輩農家の技術や経営方針を、そっくり学ぶわけではありません。ある部分は真似して、ある部分は反面教師にする。そのへんの情報収集もありますが、原則、農業は、畑が違えば方法論も全て違ってきますので、最終的には、技術は自分自身で会得するしかありません。研修は、技術習得ではなくあくまで参考になるだけです。他人の畑で3年勉強したって、自分の畑ではゼロからまたやり直しです。農業の技術は、人に習うものではないのです。言い換えれば、農業技術はその土地に付随した固有のものだとも言えるのです。
ですから、新規就農者の就農計画がしっかりしてるものであればあるほど、研修とは、コネ作り以外に、あまり意味をもたいない、ということが言えるのです。
【関連記事】就農支援資金
ここからつづき
ここで、私は、市町村の行政や農業委員会の方々に提案したいのですが、このさい、独自の営農計画を持って相談に訪れるアグリビジネスマンには、研修や信用うんぬんを無視して、思い切って、農地を使わせてあげちゃったらいかがでしょう。
もしかしたら、この人が、地域農業の救世主になるかもしれません。いや、1年で逃げるかもしれません。先に書いたように、既存農家の評判は、あまりよくないかもしれません。でも、やらせてみないと、どうなるか、わからないじゃないですか。
ビジネスのアイデアは生鮮ものです。旬とか勢いとかが、成功のためには、とても大事です。ましてや、新規就農者は、全てをゼロからはじめるので、恐ろしいエネルギーと集中力を必用とするのです。そのエネルギーを、全て一気に、自分の計画に注ぎ込みたい。それくらいの怒濤の勢いがないと、新規就農で,事業を立ち上げることはできないのです。ですから、研修で1年2年遠回りすることは、実は、かなりのマイナスなのです。なんとか、研修にこだわらず、営農計画だけで実際の就農に直行できるシステムができないものでしょうか?
鉄は熱いうちに打て!です。この都会からきたアグリビジネスマンが、ひょっとして、地域農業を救うかもしれないとしたら、少しぐらい冒険に出てもいいのではないでしょうか。もちろん、いきなり大面積を貸すわけにもいかないでしょうが。リスクの少ない範囲で、はじめは貸与して、いけそうだと見れば、権利移転できるようにしてあげればいいと思います。とにかくやらせてみて、ダメならダメで、できるだけ早く諦めさせた方が、彼のその後の人生にとってベターなわけですし。
ですから、「実績作り」という名目の研修で、アグリビジネスマンを遠回りさせるのは、誰にとっても、あまりメリットがないと思うのです。
それから、とりあえず期間限定の土地を貸し与えて、ここで実績作りさせて様子を見ようという考えも、ビジネス就農者には酷です。やはり、半永久的に小作できるところか将来的に権利移譲を前提とした貸与、ということにしてもらいたいものです。施設園芸はもちろんですが、露地栽培にしても、田畑への投資をして、はじめて農業はできます。田畑へ投入するのは堆肥だけではありません。資金や労働を投資して蓄積させていくこと、それこそが農業です。
権利関係があいまいで、将来どうなるかわからないような土地では、農業はとてもできません。私の知る限りでも、多くの新規就農者があいまいな小作状態で、畑を地主に返還せざるえない追い込まれたり,常に、畑を探していたりと、たいへん苦労しています。そんな状態では、ビジネスの計画があったとしても、実現できません。
「ビジネス的な農業を育てる」ことと「毎年1万2千人の新規就農者を確保する(政府)」ことは国是ですので(苦笑)、行政関係の方々は、そのへんを頭に入れて、新規就農者に対応していただければ、幸いです。
【参考】→農業公社を利用して農地を借地する方法
◯各都道府県にある農業公社を通して農地保有合理化事業を使えば、新規就農者が農地を機械を借り受けることが可能。
◯具体的な窓口は市町村や農協にあり、具体的な対応はさまざまである。この制度を利用して無償で土地を貸し手くれるところもあるし、窓口はあるけど、事実上機能していないところもある。
【関連記事】農業委員会
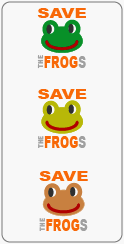
ここで、私は、市町村の行政や農業委員会の方々に提案したいのですが、このさい、独自の営農計画を持って相談に訪れるアグリビジネスマンには、研修や信用うんぬんを無視して、思い切って、農地を使わせてあげちゃったらいかがでしょう。
もしかしたら、この人が、地域農業の救世主になるかもしれません。いや、1年で逃げるかもしれません。先に書いたように、既存農家の評判は、あまりよくないかもしれません。でも、やらせてみないと、どうなるか、わからないじゃないですか。
ビジネスのアイデアは生鮮ものです。旬とか勢いとかが、成功のためには、とても大事です。ましてや、新規就農者は、全てをゼロからはじめるので、恐ろしいエネルギーと集中力を必用とするのです。そのエネルギーを、全て一気に、自分の計画に注ぎ込みたい。それくらいの怒濤の勢いがないと、新規就農で,事業を立ち上げることはできないのです。ですから、研修で1年2年遠回りすることは、実は、かなりのマイナスなのです。なんとか、研修にこだわらず、営農計画だけで実際の就農に直行できるシステムができないものでしょうか?
鉄は熱いうちに打て!です。この都会からきたアグリビジネスマンが、ひょっとして、地域農業を救うかもしれないとしたら、少しぐらい冒険に出てもいいのではないでしょうか。もちろん、いきなり大面積を貸すわけにもいかないでしょうが。リスクの少ない範囲で、はじめは貸与して、いけそうだと見れば、権利移転できるようにしてあげればいいと思います。とにかくやらせてみて、ダメならダメで、できるだけ早く諦めさせた方が、彼のその後の人生にとってベターなわけですし。
ですから、「実績作り」という名目の研修で、アグリビジネスマンを遠回りさせるのは、誰にとっても、あまりメリットがないと思うのです。
それから、とりあえず期間限定の土地を貸し与えて、ここで実績作りさせて様子を見ようという考えも、ビジネス就農者には酷です。やはり、半永久的に小作できるところか将来的に権利移譲を前提とした貸与、ということにしてもらいたいものです。施設園芸はもちろんですが、露地栽培にしても、田畑への投資をして、はじめて農業はできます。田畑へ投入するのは堆肥だけではありません。資金や労働を投資して蓄積させていくこと、それこそが農業です。
権利関係があいまいで、将来どうなるかわからないような土地では、農業はとてもできません。私の知る限りでも、多くの新規就農者があいまいな小作状態で、畑を地主に返還せざるえない追い込まれたり,常に、畑を探していたりと、たいへん苦労しています。そんな状態では、ビジネスの計画があったとしても、実現できません。
「ビジネス的な農業を育てる」ことと「毎年1万2千人の新規就農者を確保する(政府)」ことは国是ですので(苦笑)、行政関係の方々は、そのへんを頭に入れて、新規就農者に対応していただければ、幸いです。
【参考】→農業公社を利用して農地を借地する方法
◯各都道府県にある農業公社を通して農地保有合理化事業を使えば、新規就農者が農地を機械を借り受けることが可能。
◯具体的な窓口は市町村や農協にあり、具体的な対応はさまざまである。この制度を利用して無償で土地を貸し手くれるところもあるし、窓口はあるけど、事実上機能していないところもある。
【関連記事】農業委員会
コ ン テ ン ツ
スポンサードリンク
面積の単位
1反(たん)
=300坪
=10アール(10a)
=10メートル×100メートル
=1000平米
1町(ちょう)
=10反
=1ヘクタール(1ha)
=100メートル×100メートル四方
私家版 農業田舎事典
農業現場で使われる用語/田舎暮しのキーワードなどの解説集。地域性などもあるので、あくまで筆者の独断と偏見に満ちた私家版です。ぼちぼち構築中です。
リンクサイト
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
サイト内検索
リンクサイト2
農業 GardenLinker
転職・転職活動
人気blogランキング

農業ブログリンク集!
田舎暮しの夢飛行船
◯田舎暮らしに役立つ情報サイトをご紹介する「田舎暮しの総合リンク集」です。
田舎暮らしと古民家物件
【田舎暮らし友の会】

田舎暮らしのネット

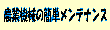
→農業機械のメンテナンス
転職・転職活動
人気blogランキング

農業ブログリンク集!
田舎暮しの夢飛行船
◯田舎暮らしに役立つ情報サイトをご紹介する「田舎暮しの総合リンク集」です。
田舎暮らしと古民家物件
【田舎暮らし友の会】
田舎暮らしのネット
→農業機械のメンテナンス
日豪EPAに関する検索結果
当サイト「田舎で農業を」を正しいレイアウトでご覧いただくには、windowsXP以上の環境が必要です。Windows2000でInternetExplorer6.0を使用した場合、正しく表示されませんので、Windows2000の方はFireFoxなどをご使用ください。
画像提供サイト
http://www.barrysclipart.com/
http://www.photolibrary.jp/
http://www.blwisdom.com/
http://www.printout.jp/clipart/
http://babu.com/~katus-gani/
http://www.kaocre.com/
http://www.barrysclipart.com/
http://www.photolibrary.jp/
http://www.blwisdom.com/
http://www.printout.jp/clipart/
http://babu.com/~katus-gani/
http://www.kaocre.com/

