|
|
|
農家になるには? 農業で田舎暮らしを満喫するには? 無計画な田舎暮らしはじめて農業経営10年目、なりゆき農家の筆者が語る、日本の田舎と農村の、夢と現実。失敗しない新規就農、成功する田舎暮らしのコツ。兼業農家からアグリビジネスまで。 |
スポンサードリンク
新規就農者が農地を手に入れる方法
[2025/10/30] [PR]
[2007/04/13] *農家になるため必要な3条資格の許可基準
[2007/04/13] *農業経営基盤強化促進法の概略
[2007/04/13] *農地をゲットするための基本手順
[2007/04/13] *農家になるため必要な3条資格の許可基準
[2007/04/13] *農業経営基盤強化促進法の概略
[2007/04/13] *農地をゲットするための基本手順
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
「農家になるための経営計画のつくり方」からつづき
注)当サイトは制度や法律に関する記述には細心の注意を払っておりますが、正確さを100%保証するものではありません。悪しからずご了承ください。最終的には公的な機関での確認を、お願いいたします。>
〓〓〓新規就農・農地取得に関する公的機関へのリンク集〓〓〓
- 原則として、下限面積50a以上(北海道は2ヘクタール以上)。例外もいろいろあるが、基本的に5反以上面積を持っている人(これから持つ予定の人)が農地購入の権利をもっている。ある程度の耕作規模がないと、農家として認められないということだ
- 新規就農者は、これから取得しようとする農地が5反以上あること
- 下限面積は市町村によって、いろいろ例外がある。ハウス栽培(集約的農業)ならもっと少ない面積でもよいとか、山奥の地区は3反でもよいなど場所により下限面積が違うこともある。
- 家と畑が離れていないこと。実際に農地を日常的に耕作管理できること。「不在地主」を防止するため
- 市町村によっては通作距離が15kmとか20kmとか1時間以内とかの具体的基準があることも。
- 原則的には耕作農地と住居は同一市町村内
- 家族のうちの誰かが年間農業従事日数が150日以上あること。
- 必要な農作業に常時従事できること・・・・要するに、農業優先で動けるということ。昼間のフルタイムの兼業は事実上不可能かも。農外収入を得る場合は、パート、季節労働、夜間勤務などとなる。配偶者の一方が昼間農外で就職しているのは問題ない
- 経営計画を実行にうつすための農業技術や、農業機械など、農業をやるための手段をもっているかどうか。
- 農業技術があるかどうかについては、事実上、研修経験や農業就労経験が問われる。経験ゼロではまずいので、週末研修でもいいから、研修実績となるものをやっておくこと。経験が少ない場合は農業に関する情報量や知識が豊富なことをアピールしてもいいかも。(【注】公的資金の融資を受ける場合は事前の研修か農業就労が必須条件)
- 大型の農業機械やたまに使う道具は、とりあえず貸してくれる人を確保しておくことで、なんとかクリア。将来的に機械を導入する資金計画は建てておくこと
農地法3条の農地売買貸借の許可基準とは
農地法3条で農地を買う・借りるばあいに、条件として、以下のような許可基準が定められている。細かい基準は、市町村によってまちまちである。最終的な許可判断は農業委員会にゆだねられる。「農家として認められる」経営面積の下限
「通作可能」であること
農業従事日数
農業をする手段を持っているか?
注)当サイトは制度や法律に関する記述には細心の注意を払っておりますが、正確さを100%保証するものではありません。悪しからずご了承ください。最終的には公的な機関での確認を、お願いいたします。>
〓〓〓新規就農・農地取得に関する公的機関へのリンク集〓〓〓
PR
「農地法3条の許可基準」からつづき
◯(市町村推奨の営農モデルをやるなら)農地が比較的借りやすい
◯1反から就農できるばあいもある
◯農地保有合理化法人は使えるかも
cehk! 貸借の場合は、農業委員会を通さず「口約束」というのもあり得る。その場合、借り手が作業を受委託していることにすれば違法ではないし、まじめに農業をやっている以上、とがめられないであろう。ただし、権利は主張できないので、口約束借地での本格的就農は勧められない。いくら地主と固い信頼関係があっても、地主の親戚やらが口を出して、突然、返せということになりがちだからだ。一方、逆兼業農家スタイルでの就農なら、この口約束借地しか方法がない。
注)当サイトは制度や法律に関する記述には細心の注意を払っておりますが、正確さを100%保証するものではありません。悪しからずご了承ください。最終的には公的な機関での確認を、お願いいたします。>
〓〓〓新規就農・農地取得に関する公的機関へのリンク集〓〓〓
農業経営基盤強化促進法による就農のポイント
◯(市町村推奨の営農モデルをやるなら)農地が比較的借りやすい
◯1反から就農できるばあいもある
◯農地保有合理化法人は使えるかも
- 農業経営基盤強化促進法による就農は、県や市町村が定める農業経営基盤強化促進の基本構想、市町村が描く営農モデルなどに沿った形で進められる
- 市町村が描く営農モデルは、地域の優良農家の事例などを参考に作られている
- 具体的には、大規模農家、集落経営、集約的農業、などが多いが、最終目標は、他産業並みの所得と労働時間にすることである。こうした理想像を「効率的かつ安定的な農業経営」と呼ぶ
- 効率的かつ安定的な農業経営を目指す人は、将来的には認定農家になることが求められる。認定農家は、地域農業の担い手としてやる気と経営能力を認めてもらうものである。
- 市町村が作成する農用地利用集積計画で認めてもらうと、3条資格でなく農業経営基盤強化促進法による就農となる。新規就農者への農地の利用権設定が農用地利用集積計画として公告されることで農地を借地でき、就農できる。
- あなたの就農計画が、3条資格によるか?農業経営基盤強化促進法によるか?どちらの法的根拠で新規就農した方がスムーズなのかの判断は、役所の担当の方にまかせてもよい
- 最終的には、農業委員会の審査は必要だ。審査基準は、3条資格の許可条件とほぼ同じである
- 農地保有合理化法人は、遊休農地などを買い集めたり借り集めたりして、一時的にストックしておく機構である。ストックのための農地保有を特別に認められている。
- 特に、大規模農業を目指す人は、ここを利用すべし
- 都道府県ごとに「農業振興公社」がある。市町村単位の農業振興公社もある。農地保有合理化法人といえば農業振興公社(=農業公社)だ。農業公社の他に、農協や市町村が農地保有合理化法人の認定を受けていることもある
- 農地保有合理化法人を利用すれば、たとえば、就農から10年間は貸してもらい、その後経営が安定したら売ってもらうことができる
- check!大規模経営の農業生産法人を作り、一定の要件をみたすと、農業公社(農地保有合理化法人)から(お金で)出資してもらえることもある
- check!市町村や地区によっては、10アールから新規就農ができるようになった
- 農地法の下限面積(=50アール)以下でも、新規就農者が正式に小作できる。ただし、利用権設定(貸借)のみである。50アール以下で買うことはできない
- 3〜4年間10〜50アール未満の面積で経営を行い、その後利用状況を農業委員会に審査され、合格すれば、長期の利用権設定が可能である
- もちろん就農計画は必要である。市町村が定める基本構想と矛盾しない計画であればスムースである
- たとえ10アールの借地でも、機械や設備などの資本装備/1年のうち農業に従事する日数/経営者の居住地と農地の距離(通勤できるか?)などの、計画実現性はチェックされるポイントである。
- 田畑を借りる場合、(1)農地法にもとづいて小作契約をする場合(2)農業経営基盤強化促進法で利用権設定とする場合がある。 、
- (1)農地法3条にもとづいて小作契約をする場合は、一度借りてしまえば、小作者に有利である。原則的に、小作契約が法定更新されていくからである。契約を解除する場合は、貸し手が都道府県知事の許可を得て事前通告するなど、手続きがたいへんである
- 農地法による小作契約を結ぶ場合、3条許可が必要である
- (2)農業経営基盤強化促進法での利用権設定は、数年間の短期間、農地を借りる簡単で気軽な方法だ。他人の畑を「ちょっと使わせてもらう」というニュアンスだ。手続きも、貸し手借り手の印鑑ひとつででき、農業委員会の審査許可を必要としない
- 利用権設定は、大規模感覚でやる場合、土地にしばられない発想でアグリビジネスをやりたい場合には向いている。じっくり土作りをして取り組みたい人には向いていない方法
3条資格との違い
農地保有合理化法人の利用
下限面積の特例措置
借地の方法‥‥利用権設定と小作契約の違い
cehk! 貸借の場合は、農業委員会を通さず「口約束」というのもあり得る。その場合、借り手が作業を受委託していることにすれば違法ではないし、まじめに農業をやっている以上、とがめられないであろう。ただし、権利は主張できないので、口約束借地での本格的就農は勧められない。いくら地主と固い信頼関係があっても、地主の親戚やらが口を出して、突然、返せということになりがちだからだ。一方、逆兼業農家スタイルでの就農なら、この口約束借地しか方法がない。
注)当サイトは制度や法律に関する記述には細心の注意を払っておりますが、正確さを100%保証するものではありません。悪しからずご了承ください。最終的には公的な機関での確認を、お願いいたします。>
〓〓〓新規就農・農地取得に関する公的機関へのリンク集〓〓〓
「農業経営基盤強化事業」からつづき
農地を手に入れるには、自分で人脈を作りなんとか見つけるというのが王道ですが、他にも、競売物件を競り落とすとか、行政に斡旋してもらうなどのコースがあります。コース別に手順を組み立てるコツをみてみましょう。
役所や農業機関へ相談する時から「面接」は始まっていると思うべし。
最低限の常識も無い人間は、門前払になってしまう。人柄もチェックされていると思え。特に市町村の農業系職員とは、末長い付き合いになるので、良い関係を作りたいものだ。 役所や農業機関の人と信頼関係を築くことが重要である
農地を斡旋・紹介してくれる機関か? 就農計画作成を手伝ってくれる機関かどうか? 情報提供をするだけか? それぞれの機関の役割をきちんと見る。
仕事として斡旋・紹介してくれる可能性があるのは農業委員(農家)や農業公社や農協(合理化法人の場合)である。 市町村農政課や県農業改良普及センターは農地の斡旋・紹介はやらない
役所や農協の人が、「個人的に」紹介斡旋してくれるケースもある。もし役所の人が、農地を斡旋してくれる場合、仕事なのか個人的好意なのかきちんと見極めること
役所や農業機関に信頼してもらうには、「経営計画」がしっかりしていることが大前提
check! いくら農業後継者不足だからといって、ゼロから手取り足取り農地取得の世話をしてくれる機関はない。最低限の情報集めや農業体験などは自分の力でやったうえで、農地関係機関を訪ねることが常識だ。
※※相対取引(あいたい)は、農地を求める人が、個人的に、貸し手や売り手をとなる農家を探し、両者の間で貸借や売買の契約を結ぶものだ。
個人どうしの取り引きだが、農地なので、農業委員会の許可が必要になる。
農業委員会を通して契約をすれば、登記を代行してくれる、免税などのメリットがある。
農地を探している段階から、農業委員会や普及センターで、
経営計画の内容を相談しておく。
▼
売ってくれる農家、貸し手くれる農家を自力で探し出す。
▼
農地が見つかれば、農業委員会に改めて相談。
▼
借り手買い手の3条資格または
農業経営基盤強化促進法の農地利用集積計画
にもとづいた資格審査
▼
登記
※就農の支援制度を使えば、登記まで農業委員会がやってくれる。登録免許料に助成金がある。売手の税金も減額される。
※土地代金をもっている人は競売を狙う手もある。競売物件で農地が出ているところは、地域差があるが、なきにしもあらずだ。農地の場合、一般の土地ほどは、地上権などがややこしくないので、競売物件というのも、充分狙える選択肢なのだ。
競売物件は、地方裁判所が管轄である。
就農候補地で、農地の競売物件がポツポツ出ているかどうか、
日頃からチェックしておく。
▼
競売物件を狙う場合は、すんなり審査が通るように、
経営計画などを綿密に準備しておく。
▼
競売物件を狙う可能性があることを
地元の農業委員会、農業委員に事前に相談しておく
▼
公示後よい物件があれば、農業委員会で買受適格証明を発行してもらう。買受適格証明は農業委員会会議で審議されたのち発行される。農地が競売物件にあがる場合、公示〜入札の間に農業委員会会議が開かれる。その会議を逃さず買受適格証明を発行してもらわない限り、入札に参加できない。買受適格証明発行審査基準は新規就農計画が認められる条件(営農計画と3条資格)と同じと考えてよい。
▼
入札(担保金が必要。担保金は後で還ってくる)
▼
競り落とし
▼
農業委員会で3条資格を認めてもらい、移転登記する。
※農業委員会や農業振興公社に農地を斡旋・紹介してもらうケース。農協が農地保有合理化法人になっている場合は、農協の畑リース・施設リースなどの新規就農コースがある可能性も。
県や市町村が農業経営基盤強化促進事業にのっとって定めている
基本構想をチェックする
▼
基本構想で描かれている営農モデルをベースに就農計画を作る
▼
就農計画の骨子を準備したうえで農地探しに入ること
▼
市町村農業委員会、農地法保有合理化法人(農業公社や農協)に相談
▼
就農地紹介の可能性があるかどうかチェック
▼
何度か足を運び自分自身のやる気や計画の内容をアピールすること
▼
ダメなら他の市町村をあたる
注)当サイトは制度や法律に関する記述には細心の注意を払っておりますが、正確さを100%保証するものではありません。悪しからずご了承ください。最終的には公的な機関での確認を、お願いいたします。>
〓〓〓新規就農・農地取得に関する公的機関へのリンク集〓〓〓
農地を手に入れるには、自分で人脈を作りなんとか見つけるというのが王道ですが、他にも、競売物件を競り落とすとか、行政に斡旋してもらうなどのコースがあります。コース別に手順を組み立てるコツをみてみましょう。
役所や農業機関へのアプローチ法の基本
最低限の常識も無い人間は、門前払になってしまう。人柄もチェックされていると思え。特に市町村の農業系職員とは、末長い付き合いになるので、良い関係を作りたいものだ。
相対取引(個人的に貸し手売り手を探す)の手順
※※相対取引(あいたい)は、農地を求める人が、個人的に、貸し手や売り手をとなる農家を探し、両者の間で貸借や売買の契約を結ぶものだ。
個人どうしの取り引きだが、農地なので、農業委員会の許可が必要になる。
農業委員会を通して契約をすれば、登記を代行してくれる、免税などのメリットがある。
農地を探している段階から、農業委員会や普及センターで、
経営計画の内容を相談しておく。
▼
売ってくれる農家、貸し手くれる農家を自力で探し出す。
▼
農地が見つかれば、農業委員会に改めて相談。
▼
借り手買い手の3条資格または
農業経営基盤強化促進法の農地利用集積計画
にもとづいた資格審査
▼
登記
※就農の支援制度を使えば、登記まで農業委員会がやってくれる。登録免許料に助成金がある。売手の税金も減額される。
競売物件の農地を狙う手順
※土地代金をもっている人は競売を狙う手もある。競売物件で農地が出ているところは、地域差があるが、なきにしもあらずだ。農地の場合、一般の土地ほどは、地上権などがややこしくないので、競売物件というのも、充分狙える選択肢なのだ。
就農候補地で、農地の競売物件がポツポツ出ているかどうか、
日頃からチェックしておく。
▼
競売物件を狙う場合は、すんなり審査が通るように、
経営計画などを綿密に準備しておく。
▼
競売物件を狙う可能性があることを
地元の農業委員会、農業委員に事前に相談しておく
▼
公示後よい物件があれば、農業委員会で買受適格証明を発行してもらう。買受適格証明は農業委員会会議で審議されたのち発行される。農地が競売物件にあがる場合、公示〜入札の間に農業委員会会議が開かれる。その会議を逃さず買受適格証明を発行してもらわない限り、入札に参加できない。買受適格証明発行審査基準は新規就農計画が認められる条件(営農計画と3条資格)と同じと考えてよい。
▼
入札(担保金が必要。担保金は後で還ってくる)
▼
競り落とし
▼
農業委員会で3条資格を認めてもらい、移転登記する。
行政や農協に世話してもらう手順
※農業委員会や農業振興公社に農地を斡旋・紹介してもらうケース。農協が農地保有合理化法人になっている場合は、農協の畑リース・施設リースなどの新規就農コースがある可能性も。
県や市町村が農業経営基盤強化促進事業にのっとって定めている
基本構想をチェックする
▼
基本構想で描かれている営農モデルをベースに就農計画を作る
▼
就農計画の骨子を準備したうえで農地探しに入ること
▼
市町村農業委員会、農地法保有合理化法人(農業公社や農協)に相談
▼
就農地紹介の可能性があるかどうかチェック
▼
何度か足を運び自分自身のやる気や計画の内容をアピールすること
▼
ダメなら他の市町村をあたる
注)当サイトは制度や法律に関する記述には細心の注意を払っておりますが、正確さを100%保証するものではありません。悪しからずご了承ください。最終的には公的な機関での確認を、お願いいたします。>
〓〓〓新規就農・農地取得に関する公的機関へのリンク集〓〓〓
コ ン テ ン ツ
スポンサードリンク
面積の単位
1反(たん)
=300坪
=10アール(10a)
=10メートル×100メートル
=1000平米
1町(ちょう)
=10反
=1ヘクタール(1ha)
=100メートル×100メートル四方
私家版 農業田舎事典
農業現場で使われる用語/田舎暮しのキーワードなどの解説集。地域性などもあるので、あくまで筆者の独断と偏見に満ちた私家版です。ぼちぼち構築中です。
リンクサイト
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
サイト内検索
リンクサイト2
農業 GardenLinker
転職・転職活動
人気blogランキング

農業ブログリンク集!
田舎暮しの夢飛行船
◯田舎暮らしに役立つ情報サイトをご紹介する「田舎暮しの総合リンク集」です。
田舎暮らしと古民家物件
【田舎暮らし友の会】

田舎暮らしのネット

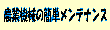
→農業機械のメンテナンス
転職・転職活動
人気blogランキング

農業ブログリンク集!
田舎暮しの夢飛行船
◯田舎暮らしに役立つ情報サイトをご紹介する「田舎暮しの総合リンク集」です。
田舎暮らしと古民家物件
【田舎暮らし友の会】
田舎暮らしのネット
→農業機械のメンテナンス
日豪EPAに関する検索結果
当サイト「田舎で農業を」を正しいレイアウトでご覧いただくには、windowsXP以上の環境が必要です。Windows2000でInternetExplorer6.0を使用した場合、正しく表示されませんので、Windows2000の方はFireFoxなどをご使用ください。
画像提供サイト
http://www.barrysclipart.com/
http://www.photolibrary.jp/
http://www.blwisdom.com/
http://www.printout.jp/clipart/
http://babu.com/~katus-gani/
http://www.kaocre.com/
http://www.barrysclipart.com/
http://www.photolibrary.jp/
http://www.blwisdom.com/
http://www.printout.jp/clipart/
http://babu.com/~katus-gani/
http://www.kaocre.com/

