|
|
|
農家になるには? 農業で田舎暮らしを満喫するには? 無計画な田舎暮らしはじめて農業経営10年目、なりゆき農家の筆者が語る、日本の田舎と農村の、夢と現実。失敗しない新規就農、成功する田舎暮らしのコツ。兼業農家からアグリビジネスまで。 |
スポンサードリンク
[新規就農概論] 進め!アグリビジネスマン
[2025/12/11] [PR]
[2007/03/09] アグリビジネスマンのための失敗しない就農地選び
[2007/03/10] 村の宿命は、どうしようもなく自分の宿命
[2007/03/10] 新規就農者の最大の切り札とは・・・
[2007/03/09] アグリビジネスマンのための失敗しない就農地選び
[2007/03/10] 村の宿命は、どうしようもなく自分の宿命
[2007/03/10] 新規就農者の最大の切り札とは・・・
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
業コース・ステップステップ2・3を先に読んでください
ビジネスとして農業経営を開始しようと考える場合、就農地を選ぶことが、たいへん重要です。
農業が、他の産業に比べて特徴的なのは、「場所に縛られる産業だ」というところです。もちろん立地条件は、どんな産業でも重要なファクターになりますが、農業の場合、より、その「場所」との関わりが、強いのです。
農業は本来、土地と生活からうまれるものです。多くの農業後継者は、先祖から受け継いだ田畑で営農をしています。農業とは、先祖代々の田畑そのものに投資するものです。「土づくり」という言葉が持っている意味は、作物がよりよく育つ土を作ることでもありますが、先祖から受け継いでいる土地そのものを守り育てていくことでもあります。
農家一戸ごとの脈々とした営みが集まって、集落を作り、集落が集まって産地を作ります。農業は、集落や産地という「場所」とも、表裏一体の関係にあるのです。
この章では、新規就農者が計画的に就農地を選ぶ方法論を検討しながら、ビジネス的な農業の本質に迫ってみようと思います。
さて、いまあなたは、ビジネス的感覚をもった新規就農者として、農業をはじめようとしています。
ここで、あなたと、既存農家(後継者)の持てるもの持たざるものを比較してみましょう。
経験や技術の面では、当然ながら、もともとの農家や後継者にはかないません。意欲や情報や柔軟性のあたりは、新規就農者の方がとりあえずフレッシュなぶん有利かもしれませんが、個人の性格にもよるので、微妙なところでしょう。
この表の中で、はっきりと言えるのは「農地」と「選択肢」のところです。ここに注目してみましょう。
既存農家の農地が◎なのは、先祖代々農地を登記簿上所有しているからだけではありません。農地は、ただの地面ではなく、「土作り」をされた生産の道具です。毎年堆肥を投資して耕耘して、その積み重ねの上に、はじめて作物が育つ「使える畑」となります。
一方、新規就農者が手に入れることができる農地は、借りるにしろ買うにしろ、その地域で、最も悪い土地であることに、ほぼ間違いありません。既存農家並みの収益を得るには、自分で土質改良することからはじめなければならないばあいがほとんどです。一見同じような畑でも、「使える畑」と「ただの農地」の差が、どれほど大きいか、やればやるほどわかるでしょう。あなたが手に入れるであろう「ただの農地」を「使える畑」にするために、新規就農者にとっては、先に述べた土作りの技術革新が絶対に不可欠です。そのための徹底した情報収集に、労力を惜しむべきではありません。
こうしてみると、場所とか土地の点では、新規就農者は、極めて不利な条件にみえますが、実は、違います。
まったく逆の見方をしてみましょう。
農地を全く持っていない新規就農者には、就農地を選ぶ選択肢があるのです。
ビジネスとして農業経営を開始しようと考える場合、就農地を選ぶことが、たいへん重要です。
農業が、他の産業に比べて特徴的なのは、「場所に縛られる産業だ」というところです。もちろん立地条件は、どんな産業でも重要なファクターになりますが、農業の場合、より、その「場所」との関わりが、強いのです。
農業は本来、土地と生活からうまれるものです。多くの農業後継者は、先祖から受け継いだ田畑で営農をしています。農業とは、先祖代々の田畑そのものに投資するものです。「土づくり」という言葉が持っている意味は、作物がよりよく育つ土を作ることでもありますが、先祖から受け継いでいる土地そのものを守り育てていくことでもあります。
農家一戸ごとの脈々とした営みが集まって、集落を作り、集落が集まって産地を作ります。農業は、集落や産地という「場所」とも、表裏一体の関係にあるのです。
この章では、新規就農者が計画的に就農地を選ぶ方法論を検討しながら、ビジネス的な農業の本質に迫ってみようと思います。
さて、いまあなたは、ビジネス的感覚をもった新規就農者として、農業をはじめようとしています。
ここで、あなたと、既存農家(後継者)の持てるもの持たざるものを比較してみましょう。
| 持ち物 | 既存農家 | 新規就農者 |
| 農 地 | ◎ | × |
| 装 備 | ◯ | × |
| 経 験 | ◯ | × |
| 技 術 | ◯ | × |
| 情 報 | △ | ◯ |
| 意 欲 | ◯ | ◎ |
| 柔軟性 | △ | ◯ |
| 選択肢 | × | ◎ |
経験や技術の面では、当然ながら、もともとの農家や後継者にはかないません。意欲や情報や柔軟性のあたりは、新規就農者の方がとりあえずフレッシュなぶん有利かもしれませんが、個人の性格にもよるので、微妙なところでしょう。
この表の中で、はっきりと言えるのは「農地」と「選択肢」のところです。ここに注目してみましょう。
既存農家の農地が◎なのは、先祖代々農地を登記簿上所有しているからだけではありません。農地は、ただの地面ではなく、「土作り」をされた生産の道具です。毎年堆肥を投資して耕耘して、その積み重ねの上に、はじめて作物が育つ「使える畑」となります。
一方、新規就農者が手に入れることができる農地は、借りるにしろ買うにしろ、その地域で、最も悪い土地であることに、ほぼ間違いありません。既存農家並みの収益を得るには、自分で土質改良することからはじめなければならないばあいがほとんどです。一見同じような畑でも、「使える畑」と「ただの農地」の差が、どれほど大きいか、やればやるほどわかるでしょう。あなたが手に入れるであろう「ただの農地」を「使える畑」にするために、新規就農者にとっては、先に述べた土作りの技術革新が絶対に不可欠です。そのための徹底した情報収集に、労力を惜しむべきではありません。
こうしてみると、場所とか土地の点では、新規就農者は、極めて不利な条件にみえますが、実は、違います。
まったく逆の見方をしてみましょう。
農地を全く持っていない新規就農者には、就農地を選ぶ選択肢があるのです。
つづく
PR
ここからのつづき
半日村というお話があります。山陰にある村で、半日しか陽が当たらず、稲の生育が極端に悪いため、村人はみな痩せている。「こんな村に生まれてしまったことは、あきらめよう」きわめて不利な村の自然環境について、みなあきらめ、そしてそれを受け入れて日々なんとか暮してる。そういう舞台設定のお話です。お話では、ある日ひとりの子供が陽を遮っている山に登り・・・・と続くのですが(『半日村』斎藤隆介作・岩崎書店→詳細はこちらから!)、ここでのポイントは、この舞台設定・・・農村はある意味どこでも半日村で、それなりのあきらめを持っている。どうすることもできない、動かし難い問題点をかかえている、というところです。
とくにその地域の地理的条件、気象条件、畑の土質や水はけなどさまざまな生産条件に関わること・・・それらは村がもっている宿命で、そこに生まれた農民には、それを変えることはできないのです。
各地域の生産者同士が何かの大会や視察で集まった時、懇親会の座で、よく自分の村の「環境の不利さ」自慢になるものです。「わしらの地域は冬の季節風が恐ろしく強い」とか「うちの地区はみな砂地で保水力がない」などなど。でも、それは、裏をかえせば、「どうしようもない環境の不利さを、いかに克服して、今、農業で生き残っているのか」、そういう自慢話でもあるのです。
農業は原則みな「なりゆき農業だ」と、前に書きました。生産する作物も、農家は自由に選べません。その土地での制限や限界がどうしてもあります。温度や日照や土質や環境など植物の生理上の作付け限界もありますが、経済的な採算面での限界もあります。消去法で消していって、「うちの村なら、この作物しかありえないべ」ということで産地が作られていきます。
このように、自分の生まれる村を選べないということは、作物を選ぶ選択肢も限られていることを意味するのです。
半日村というお話があります。山陰にある村で、半日しか陽が当たらず、稲の生育が極端に悪いため、村人はみな痩せている。「こんな村に生まれてしまったことは、あきらめよう」きわめて不利な村の自然環境について、みなあきらめ、そしてそれを受け入れて日々なんとか暮してる。そういう舞台設定のお話です。お話では、ある日ひとりの子供が陽を遮っている山に登り・・・・と続くのですが(『半日村』斎藤隆介作・岩崎書店→詳細はこちらから!)、ここでのポイントは、この舞台設定・・・農村はある意味どこでも半日村で、それなりのあきらめを持っている。どうすることもできない、動かし難い問題点をかかえている、というところです。
とくにその地域の地理的条件、気象条件、畑の土質や水はけなどさまざまな生産条件に関わること・・・それらは村がもっている宿命で、そこに生まれた農民には、それを変えることはできないのです。
各地域の生産者同士が何かの大会や視察で集まった時、懇親会の座で、よく自分の村の「環境の不利さ」自慢になるものです。「わしらの地域は冬の季節風が恐ろしく強い」とか「うちの地区はみな砂地で保水力がない」などなど。でも、それは、裏をかえせば、「どうしようもない環境の不利さを、いかに克服して、今、農業で生き残っているのか」、そういう自慢話でもあるのです。
農業は原則みな「なりゆき農業だ」と、前に書きました。生産する作物も、農家は自由に選べません。その土地での制限や限界がどうしてもあります。温度や日照や土質や環境など植物の生理上の作付け限界もありますが、経済的な採算面での限界もあります。消去法で消していって、「うちの村なら、この作物しかありえないべ」ということで産地が作られていきます。
このように、自分の生まれる村を選べないということは、作物を選ぶ選択肢も限られていることを意味するのです。
ここからつづき
限定された状況、あきらめざるを得ない運命からしかスタートできない既存の農家に比べると、新規就農者は何てすばらしいチャンスを持っているんでしょう! そして、今は、インターネットという情報の武器があります。情報化時代の今、新規就農者は、可能な限り条件を洗い出すことで、よりベターな状況で就農地を選択することができるのです。
「農業をはじめる場所を選べる自由」それは、新規就農者が持っている、唯一かつ最大の切り札です。
ただし、この切り札をいちばんはじめに切らなければなりません。ここで勝負は、決まります。
ビジネスとして成り立つ農業をするには、「就農地選び」が100%の成否を決めます。
就農地選びを失敗すると、一気にただの「なりゆき農業」に転落します。「なりゆき農業」には、経済的には厳しい現実だけが待っていることは、前に書きましたね。ビジネス的に参入して、なりゆき農業に転落する新規就農者ほど悲惨なものはないでしょう。それなりの投資をしての参入でしょうから、借金だけが残り、夜逃げするしかない、ということになります。
ですから、事前の情報集めとシュミレーションがいかに大事かわかりますよね。シュミレーションの段階で、すでにあなたのアグリビジネスは始まっているのです。「就農準備」なんて、のん気な話しではありません。シュミレーションの段階で、どんな情報に出会い、どんな情報には気づかないのか? あるいは、小さな選択の数々に、どういう決断を下すのか? 経営者であるあなたの情報処理と判断の積み重ねが、既にビジネスの成否を大きく左右しているのです。
あなたが納得いくまで解析したデーターに基づいて、経営者としての判断で絶対に成功すると言いきれる就農地を選定しないかぎり、成功することは、まずあり得ません。営農モデルの組み立てと就農地選びは、不可分の関係です。全国どこでも通用する普遍的な営農モデルは存在しません。あくまで、この地域ならこういう営農モデルが描ける、ということです。
処理しなければならない情報は、とても多いです。ほとんどパズルのように組み合わせて、なんとかモデルを作り上げながら、あなたが就農すべく就農地を割り出してください。それができないのなら、ビジネスとしての農業は、あきらめてください。
新規就農者には「農地を持っていない自由!」があります。この最大かつ唯一のチャンスをどう活かすか‥‥それがあなたのアグリビジネスの第一歩であり、全てでもあるのです。
限定された状況、あきらめざるを得ない運命からしかスタートできない既存の農家に比べると、新規就農者は何てすばらしいチャンスを持っているんでしょう! そして、今は、インターネットという情報の武器があります。情報化時代の今、新規就農者は、可能な限り条件を洗い出すことで、よりベターな状況で就農地を選択することができるのです。
「農業をはじめる場所を選べる自由」それは、新規就農者が持っている、唯一かつ最大の切り札です。
ただし、この切り札をいちばんはじめに切らなければなりません。ここで勝負は、決まります。
ビジネスとして成り立つ農業をするには、「就農地選び」が100%の成否を決めます。
就農地選びを失敗すると、一気にただの「なりゆき農業」に転落します。「なりゆき農業」には、経済的には厳しい現実だけが待っていることは、前に書きましたね。ビジネス的に参入して、なりゆき農業に転落する新規就農者ほど悲惨なものはないでしょう。それなりの投資をしての参入でしょうから、借金だけが残り、夜逃げするしかない、ということになります。
ですから、事前の情報集めとシュミレーションがいかに大事かわかりますよね。シュミレーションの段階で、すでにあなたのアグリビジネスは始まっているのです。「就農準備」なんて、のん気な話しではありません。シュミレーションの段階で、どんな情報に出会い、どんな情報には気づかないのか? あるいは、小さな選択の数々に、どういう決断を下すのか? 経営者であるあなたの情報処理と判断の積み重ねが、既にビジネスの成否を大きく左右しているのです。
あなたが納得いくまで解析したデーターに基づいて、経営者としての判断で絶対に成功すると言いきれる就農地を選定しないかぎり、成功することは、まずあり得ません。営農モデルの組み立てと就農地選びは、不可分の関係です。全国どこでも通用する普遍的な営農モデルは存在しません。あくまで、この地域ならこういう営農モデルが描ける、ということです。
処理しなければならない情報は、とても多いです。ほとんどパズルのように組み合わせて、なんとかモデルを作り上げながら、あなたが就農すべく就農地を割り出してください。それができないのなら、ビジネスとしての農業は、あきらめてください。
新規就農者には「農地を持っていない自由!」があります。この最大かつ唯一のチャンスをどう活かすか‥‥それがあなたのアグリビジネスの第一歩であり、全てでもあるのです。
コ ン テ ン ツ
スポンサードリンク
面積の単位
1反(たん)
=300坪
=10アール(10a)
=10メートル×100メートル
=1000平米
1町(ちょう)
=10反
=1ヘクタール(1ha)
=100メートル×100メートル四方
私家版 農業田舎事典
農業現場で使われる用語/田舎暮しのキーワードなどの解説集。地域性などもあるので、あくまで筆者の独断と偏見に満ちた私家版です。ぼちぼち構築中です。
リンクサイト
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
サイト内検索
リンクサイト2
農業 GardenLinker
転職・転職活動
人気blogランキング

農業ブログリンク集!
田舎暮しの夢飛行船
◯田舎暮らしに役立つ情報サイトをご紹介する「田舎暮しの総合リンク集」です。
田舎暮らしと古民家物件
【田舎暮らし友の会】

田舎暮らしのネット

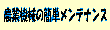
→農業機械のメンテナンス
転職・転職活動
人気blogランキング

農業ブログリンク集!
田舎暮しの夢飛行船
◯田舎暮らしに役立つ情報サイトをご紹介する「田舎暮しの総合リンク集」です。
田舎暮らしと古民家物件
【田舎暮らし友の会】
田舎暮らしのネット
→農業機械のメンテナンス
日豪EPAに関する検索結果
当サイト「田舎で農業を」を正しいレイアウトでご覧いただくには、windowsXP以上の環境が必要です。Windows2000でInternetExplorer6.0を使用した場合、正しく表示されませんので、Windows2000の方はFireFoxなどをご使用ください。
画像提供サイト
http://www.barrysclipart.com/
http://www.photolibrary.jp/
http://www.blwisdom.com/
http://www.printout.jp/clipart/
http://babu.com/~katus-gani/
http://www.kaocre.com/
http://www.barrysclipart.com/
http://www.photolibrary.jp/
http://www.blwisdom.com/
http://www.printout.jp/clipart/
http://babu.com/~katus-gani/
http://www.kaocre.com/

